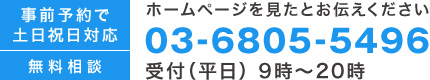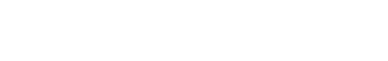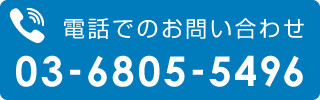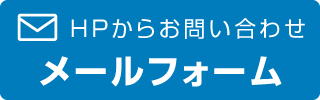Archive for the ‘会社関係’ Category
会社設立のハンコの使い分け
おはようございます。
司法書士の竹内です。
会社設立の時、法務局にいくつかの書類を作って提出します。
この時、ハンコを使い分けるのがややこしいです。
この書類は個人の実印、こっちは会社の実印という風に押すハンコが
書類によって違います。
お金を出す人(発起人)と社長(代表取締役)が違う時はお金を出す人の実印、
社長の個人としての実印、会社の実印と3つのハンコが登場します。
間違えないように気を付けるところです。
法人関係の登記は他社との契約とか税金とか、登記後も質問頂くことが多いのが
特徴ですね。
質問されるのは好きなんで専門外でも調べてお答えします。
司法書士 たけうち
社団法人、税金かからない?
みなさま、おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
今日は法人関係の話題です。
一般社団法人
公益的なイメージが得られることから、会社ではなく一般社団法人を設立する方もいらっしゃいます。
さてこの法人、税金について変わった規定があります。
わたしなりにくだいた文章で書くので、細かいところは間違いが出ると思います。
概略をつかむのにご利用ください。
この法人には「お金儲けメインの仕事以外は税金かけません」という規定があります。
お金儲け事業・・・不動産業とか製造業とかなど、国が「これがお金儲け事業」と決めている事業があります。
全部で34種類。正確にはお金儲け事業じゃなくて「収益事業」です。
もしもこの収益事業以外の仕事をしていて加えて「一定の要件」をみたせば確定申告いりません。
税務署様に売り上げ等のご報告がいらないなんて何とも違和感がありますがそういう決まりになってます。。
収益事業も、収益事業じゃない仕事もやっている法人なら、「収益事業分だけ」確定申告の必要があります。
さて「収益事業か否か」以外の一定の要件ですが、
大きいところでは「理事が3人以上いなければならない」
「理事が近い親戚ばかりだけでは駄目」だとかそんなところです。
他には「収益事業がメイン事業じゃダメ」とか
「もしも解散したら国に法人の財産を譲ることが法人のルールとなってなきゃダメ」
とかいくつかあります。
思い切ってかなり砕いて書きましたが、このルール堅い文章のままだとかなり理解しにくいです。
法人設立の際は、この辺も気を配りながらすすめます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
法人登記のついでに定款見直し
みなさま、おはようございます。
司法書士の竹内です。
役員変更の登記の際に、定款が必要になることも多いです。
また登記事項が、定款記載事項の時は、定款の内容も変更する必要があります。
そんなときは、定款全体の内容を見直しましょう。
古い定款だと現在の法律にあって無いものがあったり、最近では一般的な条文が
抜けています。
もしも変更する条文がたくさんあれば、株主総会議事録に「現行法令に照らし、第○○条、第○○条、第○○条を別紙のとおり変更する」などの書き方をすると簡便だと思います。
もちろん法人登記に伴う定款変更のお手伝いも致します。どうぞお気軽にご連絡ください。
TEL03-6407-0830
下北沢司法書士事務所 竹内友章
謄本で会社の健康診断。
商号変更登記をご依頼いただいたときのこと。
その会社さんの謄本を確認しました。
そうすると、役員変更の登記が長い間されてないことを確認。商号変更の登記と一緒に申請しました。
登記のご依頼をいただいたときには、必ず会社謄本を確認するので他の課題がないか一緒に確認します。
色々とお話しているうちに税金に話が及んで税理士さんのご紹介をすることも。ご依頼いただいたことをきっかけに他の課題についても一緒に考えるパートナーになります。
娘の誕生日プレゼント、お人形をねだられてるんですけどほとんど似たようなのがうちに2つあるんですよね。
またかと思うのですが・・わたしも子供のころゾイドってプラモデルたくさん親に買ってもらったんで一緒ですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立。現金以外も出資できる。
会社設立時に資本金がいくらか決め、出資金を振り込んだことを証明する通帳のコピーを添付して法務局に提出します。しかし車や不動産など、現金以外のもので出資することも可能です。「現物出資」といいますが、この場合、現金の場合には発生しない少し特殊な手続きが必要になります。出資した財産の価値が、本当の価値より不当に大きく評価されていないか確認するためで、裁判所に「検査役」を選任を申し立て調査をさせなければなりません。ただし、いくつか例外もあり出資された財産の価格を500万円以下として定款に記載した場合や、弁護士・公認会計士・税理士などに調査をさせた場合などがあります。このように、現金よりは手続きの数が増えますが車などを出資して会社を設立することも可能です。詳しくはご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
電子委任状の普及の促進に関する法律
「森友学園」「加計学園」「テロ等準備罪」「都議選での自民党惨敗」このあたりが、最近メディアで報道される政治の話題の中心だったと思います。しかし地味に企業間取引、官公庁と企業の取引、そして司法書士業務にも影響が出そうな法案が成立していました。「電子委任状の普及の促進に関する法律」という法律です。A社とB社が契約を結ぶ場面を想定してみます。A社が代表取締役でなく社員に契約を任せたとすると、B社としては「この社員は確かにA社から契約を締結する権限を与えられている」と確認できなくては心配ですね。紙の契約書なら代表取締役が持っている会社実印を押したり、会社から社員に対する業務権限を委任する旨の書面を確認したりすることができます。ところがオンライン上で契約をすると、このような確認をすることができません。そこでこの法律では、代表取締役が「電子委任状取扱事業者」という国から認定を受けた業者に電子委任状の保管させ、契約の相手方がそれを閲覧することにより契約の相手方は「この契約で、確かにこの社員に契約権限を委任しているな」と確認ができ、その社員が電子署名をすることで契約を成立させることができます。実際、どこまで利用されるのかわかりませんがそのうち印鑑が無くなるときがくるのかもしれません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立時の資本金・発行株式数
会社設立時に決めなければならない資本金。よく「いくらにすればいいですかね?」とご質問いただきますが、特にこれといったルールはありません。開業準備(テナント代、コピー機などの事務機器、その他会社を始めるに際して必要なものを揃える)に必要なお金と、当面の運転資金を資本金とすればいいと思います。開業に必要な資金は業種によって大きく違いますし、当面の運転資金もどれくらい用意するのか業種や経営者の考えで変わりますので相談しながら決めましょう。ただし資本金が1000万以上だといきなり消費税の課税事業者になってしまいます。また、発行する株式の数も社長さんと相談しながら決めていきます。資本金を株式の数で割った値段が一株あたりの値段になります。1株いくらであろうと大きな問題はないですが、あまり株価が高くなると将来、出資者が募りにくくなります。資本金が100万円で1株しか発行しなかったら、「1株100万円」なので、出資なされる方は事実上100万円以下の出資は考えにくいでしょう。最初の出資者である会社設立者が100万円以下で出資させては損をしてしまいます。100株発行して「1株1万円」としといた方が出資しやすいですね。もちろん、皆さんの会社の株価はどんどんあがると思いますので、会社設立時の金額は将来の出資者にとって最低の金額です。一株1万円若しくは千円としとくのが妥当かなと思います。
当事務所が参加する会社設立用の特設サイト。税理士さんも参加してます。http://start-setagaya.com/
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
株式会社-残余財産の分配請求権
株式会社は当然、株を発行しますが同一の会社において数種類の株式を発行することも可能です。「普通株式と比較して、どのように違う株式を発行できるか?」について会社法108条において、9種類定められています。その中の1つ「残余財産分配請求権の優先株式」。いつか会社を清算するときに、普通株式の株主より優先して残余財産の分配を受けられます。ちょっとややこしいですが、①創業して②会社が成長し出資者が登場③他の会社に、自社を売却する(吸収合併される)という展開を想定してみましょう。1人で出資して資本金100万円の会社を創業したとしても、出資者が現れる時は企業価値が10倍の1000万円になっているかもしれません。新たな出資者は創業者の10倍のお金を出して株式を買うことになります。じゃあこの会社を「1500万で買います」という方が現れたらどうでしょうか?創業者と出資者で半分づつ株式をもっていたらそれぞれ750万円づつお金を手にします。創業者は「750万円ー100万円」で600万円得します。しかし、出資者は「750万円ー1000万円」で250万円損します。これでは出資者は売却に同意しません。しかし出資者の手にする株式が「会社を清算するときはまずは、1000万円優先して配当を受ける。残りの財産を普通株式の株主と1対1で分ける」との内容だったらどうでしょうか?まずは出資者が投資額の1000万円を手にし、残った500万円を2人で分けます。創業者は500万の半分の250万円から創業時に投資した100万円をひいて150万円のプラス、出資者は250万円のプラスなので創業者も出資者も得をすることになりますね.これなら話がまとまるかも知れません。仮定に仮定を重ねてしまってますが、こんなことも起こりえます。出資者と投資契約を結ぶときは契約内容を良く擦り合わせる必要があると思います。
仕事上、よくいく法務局世田谷出張所の写真です。この建物の2階に法務局がありますが、新しくとても綺麗な建物です。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立時の届け出
会社設立した直後に、税務署関係に必要な届け出をざっくりとまとめてみます。
①法人設立届出書・・・会社の概要を税務署にお知らせする書類。設立日から2か月以内が期限。必ず提出が必要。
②法人設立届出書(地方税)・・・設立届出は地方税用にも必要。都内なら都税事務所が管轄。市役所に届ける場合もある。
③給与支払事務所の開設届出書・・・給与等の支払いを行う場合に税務署に届け出る。給与支払いを取り扱うようになってから1カ月以内。事実上必ず提出が必要
④青色申告の承認申請書・・・会社設立から3カ月以内に税務署の届け出。義務ではないが青色申告の特典を受けるため、通常は提出する。
⑤源泉所得税の納期特例の申請書・・・給与の源泉所得税等の納付期限を月に1回でなく、半年ごとに行うための申請書。従業員10人以内のみ申請できる。
他にも個人事業主から法人になった場合は個人事業主の廃業届、資本金が1000万円以上の場合は消費税課税事業者の届け出なども必要です。税務署関係の主要なものだけでも結構ありますね。また、年金事務所や労働基準監督署向けの届け出もあります。この辺は司法書士の分野ではありませんが、できる限りのアドバイスや専門家のご紹介でお手伝いします。
会社設立サイト 税理士さんが参加の上、報酬を減額してます。http://start-setagaya.com/
今日も暑いですね。もう夏になったんでしょうか?
下北沢司法書士事務所 竹内友章
事業年度の決め方
会社設立時に決めなければならないことに、事業年度があります。4月から3月あるいは1月から12月が多いと思いますが、いつでも会社の任意の時期に決められます。ただ、事業年度の終わりが決算日になるので、その点を踏まえて決めた方がいいと思います。例えば、①決算月から2か月以内が確定申告の期限なので、繁忙期と確定申告の時期をずらし忙しくなりすぎないようにする。②在庫を抱える仕事内容であれば、棚卸作業に備えて在庫が少ない時期を選ぶ③1期目をなるべく長くするようにする(会社を5月に設立して6月が決算月だと、設立してすぐ確定申告なので大変です。また消費税免税事業者である期間を長くとるために1期目を長くした方がいい場合も考えられます)ざっとこんなポイントがあげられます。相談しながら決めていきましょう。
上のリンク、当事務所が参加する会社設立パッケージのサイトです。税理士さんも参加しています。
下北沢司法書士事務所 竹内友章