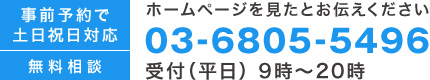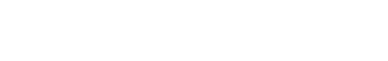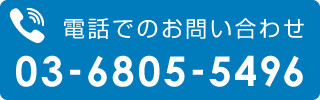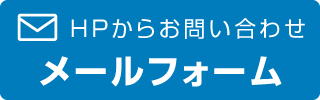Archive for the ‘相続・遺言’ Category
古い実家×相続×売却=税金の控除!?
こんにちは!
東京の司法書士、竹内と申します。
不動産の名義共有の防止や予防、相続、大家さん向けの法律相談に取り組んでいます。
「空き家問題」
テレビやネットでこのテーマを目にすること増えました。
あまり知られてないですが、このテーマに関係して税金が控除される制度があります。
相続で取得した、昭和56年5月31日以前に建築された空き家になってしまう不動産を
売却すると、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度です。
都心にお住いの方が、相続で取得した実家を売却するときに使えそうな制度ですね!
詳しい要件は国税庁のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
期限が切られており、平成31年12月31日までに売却しないと使えません。
こういう特例は見落とすとお金を損してしまいます。
気をつけたいものですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺言や信託ーお子さんが喜びます。
今日は日曜日。
楽しい休日をお過ごしでしょうか?
司法書士の竹内と申します。
相続などで生じる不動産の共有名義の予防や解消、認知症の法律的な事前や事後対策、大家さん向けに入居者死亡や家賃滞納などの対応をメイン業務にしています。
さて遺言や信託といったいわゆる相続対策、信託などの老後に備えた対策は何のためにやるのでしょうか。
税金やお子さん同士の意見の食い違いを防ぐなど色んな理由がありましょうが、一番は
「お子さんや奥さん、旦那さんに喜んでもらう」
ことです。
わたしの父も将来を考え、老後や相続発生後にわたしたち兄弟が困らないように対応しておいてくれました。
なかなか本人に伝えるのは照れ臭いですが、感謝でいっぱいです。
父は「細かいことは分からないけどこのままじゃやばそうだな・・・」といういわば「勘」から対応を
とってくれました。
人にとって「経験」や「勘」ってすごいものだと思います。
「このままだと、まずい気がする・・・」そう思われた方。
おそらくそれ、当たってます。
どんなところがまずいのか?
どう対応すればいいのか?
わたしがひも解くお手伝いを致します。
ご相談無料。
「無料で仕事になるわけがない。結局、理由をつけて請求するんだろう」
と思われるかも知れませんが心配ありません。
登記や後見など実務が発生するときは、お見積もりを作成して料金を提示します。
いつでもお気軽にご連絡ください。
TEL03ー6407ー0830
今日の昼間、凄くあたたかったですね。ダウンジャケットの出番ももうすぐなくなりそうです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。
こんにちは。
司法書士の竹内と申します。
東京で不動産の共有状態の解消、
賃貸物件での入居者死亡後の解約手続きをメイン業務としています。
さて、相続対策のご相談も良くいただきます。
そこで、意外と多いなと感じたのが
「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配なされているケース」
おそらくは、
「意見が非常にいいづらい」
「しかしながら、自分の家庭に大きな影響がある」
この2つが理由だと思います。
相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので「いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう」
と思う。
しかしながら奥さん旦那さんは自分が主導権を握れないどころか関与もしにくい、しかし大げさにいえば
家庭の運命に大きく関わる・・・。
この状況にやきもきして相続問題が頭から離れなくなってしまうのではないかと思います。
プラスの財産がないだけならまだしも借金が残っていたりしたら、しかも借金に気が付くのが
遅れて相続放棄できなかったら・・・。
そう考えると確かに怖いでしょう。
相続人になる方の奥さん、旦那さんとしてはまずは相続人ご本人の興味を持ってもらうことが大事
だと思います。
機嫌を見計らないながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。
もしも「どんな切り口から話していいか分からない」という方は是非、ご相談ください。
不動産から切り出す、株から切り出す、あるいはお義父さま、お義母さまの趣味から
切り出すなど、いい方法を一緒に考えます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続登記が難しい理由。
みなさま、おはようございます。
ブログをご覧頂きありがとうございます。
相続発生後に必要な不動産登記。
でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。
それらと相続登記の違いについてお話します。
「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは
役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は
自分で申請書を作らなければなりません。
また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。
「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。
なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。
平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して
みるのもいいかも知れません(電話予約要)。
当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。
司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。
今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続と事業承継
会社経営されている方の相続問題は複雑になりがちです。
なぜなら、
「個人財産と会社の財産の区別が明確につけられないから。」
個人名義の不動産を事業用に使っている場合などが良くあるケースで、
都内ですと歯医者さんなどの個人開業医の方に多く見られるケースです。
事業用の財産を全部後継者に譲ると、他の子供たちにとって不公平・・・。
かといって現金もそんなに用意できないし。
そういうときは、生命保険を活用するやり方もあるようですね。
また、税金対策としても基本的に一度に多額の財産を移すより、
少しづつ財産を動かす方が有効な場合が多いようです。
少しづつうつすためには、はやめに対応するのに越したことはないです。
わたしは、親身になってくれる税理士など自信をもってご紹介できる他の専門家もご紹介致します。
紹介料は当然、無料です。
またご相談も相談料や時間制限は設けていませんし、自分の仕事が欲しいがために必要もない法的サービスを
すすめたりしません。
あなたのための司法書士です。
どうぞいつでもお気軽にご連絡ください。
03-6407-0830
借地権の相続
建物は自分のもの、土地は借りている状態の「借地権付建物」。
割安の土地の賃料で、都心に家が持てる魅力的な選択肢です。
しかし、所有者の方が高齢になると考えなければならないのが相続問題。
借地権者に相続が発生して借地権が数人に相続される・・・。
そうするとその建物を売却などの処分をするときは、数人の相続人の
全員の合意で行います。
何らかの事情で相続人の1人と連絡がとれないと、失踪宣告などの
法的手続きが必要になってしまうことも・・・。
ただちょっとした対策で対応可能です。
遺言で、その建物に実際に住む相続人に権利を集約したり、
日ごろから相続人間の連絡を密にしたり・・・。
できれば、問題発生前に予防しておいて将来の安心に
繋げたいものです。
今日は「文化の日」。軽く調べると憲法が公布された年のようです。
全く文化的ではない私ですが、なにか文化っぽいことしましょうかね。
映画でも見ればいいかな・・・。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
不動産と相続放棄
相続放棄は、注意しなければならないこともあります。
見落としがちなのが「相続放棄は自分の分しかできない」
ということ。
何となく、相続放棄すればご兄弟も安心だと思うのが普通かも知れませんが、
他の相続人の方の分の相続放棄はできません。
もしも相続放棄をするときにはご兄弟など他の相続人の方とよく話し合って、
他のご兄弟の相続放棄についても良く考える必要があります。
もう10月終わりですね。なにか秋らしい天候の10月ではなくて少し寂しいです。
11月は秋を楽しめるといいですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
謄本みないとわからない。
相続登記は「相手」のいない登記です。会社をはじめとした法人の登記も相手がいません。。これに対して売買とか贈与で登記すると「売主」「買主」などの相手がいます。相続登記をご自身でなされる方が多いのは、相手がいないこともあると思います。相手がいたら、当事者の一方が相手の登記も申請するのはかなり場面が限られるでしょう。法的には可能でも、現実的には難しいと思います。
相続登記は個人向けに易しく解説した本も多く、ご自身で登記される方にとって心強いと思います。しかし、なかなか本を読んだだけでは分かりにくいことも・・・。亡くなられた方名義の担保権が設定されていたり、登記簿上の名義が亡くなられた方ではなく先代の名義になっていたり。そうなると「どの登記をどの順番で」申請するか検証が必要になったり、申請書等の書類の書き方も複雑になったりします。登記簿を見て「ちょっとややこしそうだな」と思ったら司法書士若しくは法務局に相談しましょう。当事務所では登記の枠組みを確認する作業は無償です。
大雨の中、カッパを着て「投票所はこちら」と書いた紙をもって道案内している人をみかけました。仕事でやってるとはいえみんなの為に頑張る姿は立派で、思わず会釈してしまいました。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続人が行方不明の場合
相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議をするのに手続きをとる必要があります。要件を満たせば失踪宣告の制度を使うことが多いと思いますが。この制度は法律上、行方不明者を死亡したと考える制度です。また行方不明の方に借り入れ金が多い場合は、行方不明者の相続放棄も検討する必要があるなど、状況によって取るべき手段も変わります。いずれにしろしっかり手続きしないと、相続不動産の売却などができず塩漬けになってしまうので早めに対処するべきでしょう。失踪宣告の手続きは司法書士なら書類作成、弁護士なら代理をすることができます。具体的な違いが知りたい、制度について詳しく知りたい方はお気軽にお電話ください。土日でも大丈夫です。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
不動産と相続放棄
相続放棄をする場合、財産に不動産があったら要注意です。民法940条の規定により、相続放棄をした人には、次の相続人の方が引き継ぐまでその相続財産を管理する必要があります。次の相続人もいなかったら「相続財産管理人」を裁判所に選任してもらい、その人に不動産を処分してもらうまで管理責任は続きます。相続財産管理人は裁判所に多額の予納金が必要になる上、選任まで手続きに最低10カ月がかかります。そのため、実際にはこのような手続きをなかなかとれず不動産の権利が宙ぶらりんになってしまうことも多いです。「放棄したらすべて終わり」というわけではないので気を付けなければなりません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章