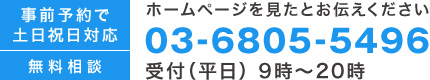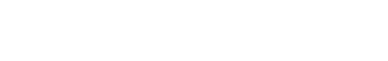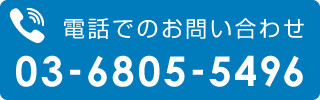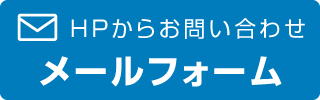Author Archive
抵当権の抹消
無事、住宅ローンを払い終えると抵当権を抹消するための書類が金融機関から届きます。これは、「今までご自宅を担保にとっていましたが、全額お金を返してもらいました。つきましては登記簿の担保の部分を消すための書類をお送りします」ということです。この時に注意しなければならないのは、住所移転の登記が必要になるケースが多いことですね。ご自宅を購入した時点では、住民票は引っ越し前のご自宅にあることが多いですが、その後購入された現在のお住いに住民票を移されていると思います。そのため、抵当権を消す登記の前に住所が移ったことの登記申請が必要になることがあります。抵当権の抹消登記は期間的な制限はありません。すっかり忘れてしまって長い間放置することも多いですが、万が一、相続が発生してしまったりすると抵当権の抹消もやや複雑な手続きになります。極力早めに抹消登記をした方がいいですね。
今日はかなりいい天気ですね。毎日こんな陽気だと嬉しいですけどね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
有限責任事業組合(LLP)
プロジェクトありきで色々な会社の知見や、技術を集約したいときに使う有限責任事業組合(LLP)という手法があります。法人格がないため簡易的な運営ができる、LLPそのものに対する課税はなく組合員それぞれに直接課税される等が特徴。LLPを設立する場面として、いくつかの中小企業が共同して出資し、完成した試作品を大企業に提案するときなどがあり得ます。このように「こんな状態を実現したい」というのが明確になれば株式会社や合同会社とは違った法手法が有効なこともあるかもしれません。もし宜しければ実現したいことをお聞かせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
権利証を無くしたとき
不動産売買の際に必要になる登記識別情報。売主様が対象不動産を手に入れた時期によっては登記済証(権利証)です。とても大事な書類とは分かっていながら、紛失してしまうことがあると思います。引っ越しのタイミングで紛失してしまう方が多いかもしれません。ではこの登記識別情報若しくは権利証が無い場合、どうしたらいいのか?いくつか方法がありますが、もっともよくつかわれるのが司法書士がご本人確認情報を作成し、それを登記識別情報に代用する方法です。司法書士が「この方は間違いなく不動産の名義人ご本人で、今回の取引で買主様に不動産を譲渡する意思があります」ということを司法書士が法務局に証明するようなイメージですね。このように登記識別情報、権利証を紛失しても対処法はありますが、やはり大切に保管したいものです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
役員任期
会社設立の際に、ご依頼人の方とご相談しなければならないことの1つが役員の任期です。原則2年ですが、最長10年まで伸ばすことが可能。任期を伸ばしておけば、その分役員改選と登記の手間が省けます。お1人で会社を始める場合はこれで問題ないかなと思いますが、役員の方が2人以上いる場合は注意が必要です。もしも役員同士の方向性が違っても、辞任しない限り任期までは一緒に頑張ることになるので・・・。場合によっては「解任」することも可能ですが登記簿に「解任」と記録が残るので、対外上の印象が良くありません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立時の税金の節約
皆さんが株式会社を作ろうと思ったら登録免許税という税金が基本的に15万円かかってしまいます。
ただ、一定の要件を満たせば7万5000円節約できます。ものすごくざっくりですが、
①会社を作る本店予定地の自治体が、「創業支援事業計画」の認定を受けている
(受けている自治体が多いと思います。)
②その自治体の「特定創業支援事業」を受ける(セミナー、窓口相談等)
③支援を受けたことの証明書を自治体からもらって、法務局に提出
こんな流れです。
お金がかかることも多いでしょうし、時間もかかるので
お得な感じはそんなにしないかもしれません。
世田谷区役所の関連リンク、張っておきます。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/116/294/295/d00144901.html
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
ご挨拶
この度、ホームページを作成致しました。どうぞよろしくお願いいたします。
このブログでもお役に立てる情報発信をこころがけて参ります。
下北沢司法書士事務所 竹内 友章