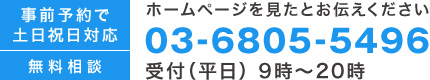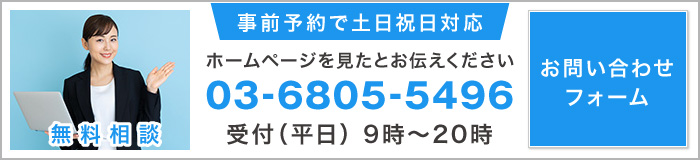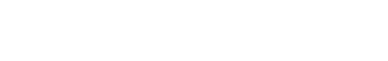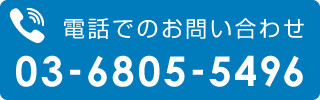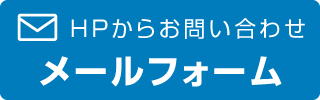相続は「計算」だけでは終わらない?まず知っておきたい2つの考え方
「法律で決まった割合があるはずなのに、なぜ話し合いがまとまらないのだろう…」
ご相続の問題に直面された多くの方が、このような壁に突き当たります。相続は、財産を数字で分割するだけの単純な「計算」ではありません。そこには、故人様への想い、ご家族それぞれのこれまでの人生、そして将来への願いが複雑に絡み合っています。
私たち下北沢司法書士事務所は、代表司法書士(東京司法書士会所属)が不動産会社での実務経験と心理カウンセラーの資格を有しており、単なる法律手続きの専門家としてだけでなく、ご家族の心に寄り添うパートナーとして、これまで多くの相続問題と向き合ってまいりました。
この記事では、まず相続計算の基本となる2つの「モノサシ」をご説明し、その上で、なぜ計算通りに進まないのか、そしてどうすれば円満な解決に至れるのかを、具体的なケースを交えながら丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を客観的に見つめ、次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。

目安となる「法定相続分」
法定相続分とは、故人様が遺言書を遺されなかった場合に、民法で定められた遺産分割の「目安」となる割合のことです。誰が相続人になるか(法定相続人)によって、その割合は変わります。
【法定相続人の順位と法定相続分】
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者:1/2、子:1/2(複数いる場合は全員で1/2を均等に分ける) |
| 配偶者と親(直系尊属) | 配偶者:2/3、親:1/3(複数いる場合は全員で1/3を均等に分ける) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は全員で1/4を均等に分ける) |
| 子のみ | 子がすべて相続(複数いる場合は均等に分ける) |
ここで重要なのは、法定相続分はあくまで「目安」であるという点です。相続人全員が納得し、合意すれば、この割合とは異なる内容で遺産を分割することも全く問題ありません。法律は、ご家族の話し合い(遺産分割協議)による円満な解決を最も尊重しているのです。
最低限の権利「遺留分」
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取得権であり、被相続人が遺言等で特定の者に偏って遺贈した場合でも、対象相続人は遺留分侵害額請求により金銭で遺留分を回復できます。ただし計算方法や基礎財産の範囲、時効など法的要件があり、請求が自動的に実現するわけではありません。
【遺留分が認められる相続人とその割合】
- 対象者:配偶者、子(またはその代襲相続人)、親(直系尊属)
- 対象外:兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 割合:
- 直系尊属のみが相続人の場合:遺産の合計額に対する遺留分は1/3(父母が2名いる場合は合計1/3を均等に分けます)
- それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):各人の遺留分は、その人の法定相続分の1/2
法定相続分との大きな違いは、遺留分は自動的に受け取れるものではなく、権利を持つ人が「遺留分を侵害している相手方に対して請求する(遺留分侵害額請求)」ことによって初めて効力が生じるという点です。つまり、請求するかどうかは、権利を持つ人の意思に委ねられています。
【ケース別】相続財産の基本的な計算方法
ここでは、具体的な家族構成を例に挙げて、相続財産の計算方法をシミュレーションしてみましょう。ご自身の状況と照らし合わせながら、大まかな金額をイメージしてみてください。計算の対象となる財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれることに注意が必要です。
法定相続分の計算シミュレーション
【例】遺産総額が5,000万円の場合
ケース1:相続人が配偶者と子2人
- 配偶者の法定相続分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
- 子1人あたりの法定相続分:5,000万円 × 1/2 ÷ 2人 = 1,250万円
ケース2:相続人が配偶者と故人の父
- 配偶者の法定相続分:5,000万円 × 2/3 ≒ 3,333万円
- 父の法定相続分:5,000万円 × 1/3 ≒ 1,667万円
ケース3:相続人が子3人のみ(配偶者は既に他界)
- 子1人あたりの法定相続分:5,000万円 ÷ 3人 ≒ 1,667万円
遺留分の計算シミュレーション
【例】遺産総額6,000万円。故人が「全財産を長男に相続させる」という遺言を遺していた。相続人は配偶者、長男、次男の3人。
- まず、本来の法定相続分を計算します。
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 長男:6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
- 次男:6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
- 次に、各人の遺留分を計算します(法定相続分の1/2)。
- 配偶者の遺留分:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 次男の遺留分:1,500万円 × 1/2 = 750万円
この場合、配偶者は1,500万円、次男は750万円を上限として、遺産を多く受け取った長男に対して金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持ちます。なお、遺留分を計算する際の基礎財産には、相続開始前10年以内に行われた相続人への特別な贈与(生前贈与)なども含まれる場合があり、実際の計算はより複雑になることがあります。
不動産がある場合の評価額はどう計算する?
相続財産に不動産が含まれる場合、その「価値」をいくらと見積もるかで、話し合いが難航することが少なくありません。不動産の評価額には、主に以下の4つの基準があります。
- 固定資産税評価額:市町村が固定資産税を課税するために定める評価額です。土地・家屋は原則として3年ごとに評価替えが行われますが、新築・増改築や地目変更などがあった場合は、基準年度以外でも評価替えが行われることがあります。
- 路線価:国税庁が相続税や贈与税を計算するために定める土地の評価額。主に市街地で設定されます。
- 公示価格:国土交通省が公表する土地取引の目安となる価格。
- 時価(実勢価格):実際に市場で売買される価格。不動産会社の査定額などがこれにあたります。
どの評価額を用いるかについて法律上の決まりはありません。遺産分割協議においては、相続人全員が合意した金額が、その不動産の評価額となります。
不動産会社での勤務経験から申し上げますと、もし不動産を売却して金銭で分ける(換価分割)のであれば「時価」を、誰かが相続して住み続けるのであれば、比較的低額になりやすい「固定資産税評価額」や「路線価」を基準に話し合うなど、目的によって使い分けるのが現実的な落としどころを探る一つの方法です。どうしても合意できない場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼することもあります。不動産の分け方は、その後の不動産の名義変更(相続登記)手続きにも関わってきますので、慎重な判断が求められます。

なぜ?相続が「計算通り」にいかない5つの理由
法律で計算の目安が示されているにもかかわらず、なぜ相続は「争族」とも呼ばれるほど揉めてしまうのでしょうか。その背景には、数字だけでは割り切れない、ご家族ならではの事情や感情が隠されています。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士として、その深層にある理由を5つの側面から解説します。
①財産が分けにくい(不動産など)
最も多い原因の一つが、遺産の大部分をご自宅の不動産が占めているケースです。預貯金のように1円単位で分けられないため、「誰が相続するのか」「どうやって公平に分けるのか」という問題が生じます。
- 「売却して現金で分けたい」相続人
- 「思い出の家だから住み続けたい」相続人
こうした意見の対立は、容易に解決しません。住み続ける場合は、他の相続人に対して代償金(自分の相続分を超えて不動産を取得する代わりに支払うお金)を支払う必要がありますが、その資金を準備できないことも少なくありません。物理的に分けられない財産は、家族の想いが対立する火種になりやすいのです。
②生前の貢献度(介護など)への不満
「私は長年、親の介護を一身に引き受けてきた。何もしてこなかった兄弟と同じ割合なのは納得できない」というお気持ちは、非常に切実なものです。このような生前の特別な貢献を金銭的に評価し、相続分に上乗せを主張することを「寄与分」と言います。
しかし、この寄与分が法的に認められるためのハードルは、実はかなり高いのが実情です。通常の親子間の扶養の範囲を超える「特別な貢献」であったことを客観的な証拠で示す必要があり、感情的な「大変だった」という想いと、法的な評価との間には大きな隔たりがあります。このギャップが、貢献した側の不満と、他の相続人との溝を深める原因となります。
③生前の援助(特別受益)への不公平感
「兄だけ、大学の学費や結婚資金を親から援助してもらっていた」「妹は家を建てる時に多額の贈与を受けていた」。過去の特定の相続人だけが受けた援助(特別受益)は、他の相続人にとって大きな不公平感につながります。
民法では、この特別受益を遺産の前渡しとみなし、相続財産に持ち戻して計算することで公平を図る仕組みがあります。しかし、過去の贈与の事実を証明することの難しさや、「あれは援助ではなくお小遣いだ」といった認識の違いから、かえって議論が紛糾し、新たな争いの種になることも少なくありません。
④相続人同士のコミュニケーション不足
相続をきっかけに、それまで表面化しなかった家族間の長年の不満や確執が噴出することがあります。特に、相続人同士が疎遠であったり、もともと関係性が良好でなかったりすると、冷静な話し合いは困難を極めます。
お互いの状況や考えを理解しようとせず、自分の権利主張ばかりが先行してしまうと、遺産分割協議はあっという間に行き詰まります。相続は、法律問題であると同時に、家族関係の総決算という側面も持っているのです。コミュニケーションの不足は、合理的な判断を妨げる最も大きな障害の一つと言えるでしょう。
⑤特定の相続人による遺産の囲い込み
故人様と同居していた相続人が、通帳などの財産を管理し、他の相続人にその内容を一切開示しない、というケースも散見されます。ひどい場合には、生前から財産を使い込んでいたのではないか、という疑念が生じることもあります。
情報が不透明な状況では、他の相続人は何を基準に話し合えばよいのか分からず、不信感と無力感に苛まれます。このような一方的な囲い込みは、信頼関係を根本から破壊し、円満な解決を絶望的にしてしまいます。

計算と感情の狭間で。円満解決の前提となる相続財産の把握
ここまで見てきたように、相続は計算と感情が複雑に絡み合う難しい問題です。しかし、解決への道筋は一つではありません。ここでは、ご自身の状況に合わせて検討できる3つの選択肢をご紹介します。大切なのは、ご家族にとってどの方法が最も幸せな未来に繋がるかを考えることです。
ステップ1:実は一番重要!正確な財産状況の把握
相続で意見がまとまらない時、「とにかく話し合いが大事」と思うかも知れません。あるいは「自分で話し合うのは大変。弁護士さんに調停をお願いしよう」と考える方もいることでしょう。
でもちょっと待ってください。話し合いをするのにもその前提となる事実認識がお互いに違ってしまうと、お互いにすれ違うばかりです。話し合いがうまくいかない時はそもそもどの財産がいくらあるのか棚卸をまずはしてみましょう。
ここでポイントとなるのは「どの時点の数字や財産内容を把握するか」です。亡くなった後も介護費や入院費の支払いがあったり、しばらくの間は数字が落ち着かないものです。
そこでまずは「相続開始の日」つまり、亡くなった日の数字を把握しましょう。そして、把握した預貯金額や株式の数、不動産などを落とし込んだ「財産目録」を作成します。
目録を作って財産内容が一目で分かる状態で可視化するだけでも、ずいぶんとスッキリするものです。自分の気持ちも落ち着くかも知れません。話し合いがうまくいきそうもないときは、まずは財産内容を整理することからはじめるのも良いと思います。
ポイント2:財産調査は他の相続人の協力なしにできる。
銀行・信用金庫などの金融機関は、名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結してしまいます。そうすると遺言や遺産分割協議で預貯金の帰属先が決定したことを確認するまで、そのまま凍結したままです(一部例外有)。しかし、銀行が預貯金を凍結するといってもそれは下せないというだけです。財産内容を教えてくれないわけではありません。残高の照会等や過去の取引履歴の取り寄せには、協議書や遺言が無くても手続きを踏めば応じてくれます。
そして、財産調査だけであれば相続人全員の同意が必要なわけではありません。相続人の1人からの求めにも応じます。不動産情報も登記情報などから求めることができますし、いざとなれば他の相続人の協力なしに、大体の財産内容は把握することができます。
もしも他の相続人が遺産の状況を掌握していて教えてくれないことにお悩みの方は、司法書士の協力を得るなどして財産状況を自分で把握するのも一案です。
ポイント3:「遺留分を請求しない」という選択肢
前述の通り、遺留分は「請求して初めて発生する権利」です。法律で保障されているからといって、必ずしも行使しなければならないものではありません。
遺言によって財産を受け取った相続人が、その財産(特に自宅不動産)を失うことなく生活を続けられるように、他の相続人があえて遺留分を請求しない。実はこういうケースは良くあります。みなさん遺留分など全く意識することなく、自宅不動産を同居している親族が相続してそれで終わりというケースなどです。
遺留分の知識があると、とかく権利を行使しなければと思う方もいらっしゃいます。しかし遺留分を行使しない相続など普通のことですし、行使するにも具体的に遺留分に相当する金額はいくらなのか請求する方が計算しないと、「で、分かったけどいくら欲しいの?」と言われるだけです。遺留分は請求権があるといっても実際に使うとなると大変です。必ず行使するようなものでもありません。
相続の計算と手続き、一人で悩まずご相談ください
この記事では、相続における法定相続分や遺留分の計算方法から、不動産の評価、特別受益や寄与分といった論点、そして計算通りにいかない理由と解決策まで、網羅的に解説してまいりました。
お分かりいただけたように、相続は単なる計算問題ではなく、法律、不動産、そして何よりご家族の感情が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。一つボタンを掛け違えるだけで、解決が遠のいてしまうことも少なくありません。
もし、あなたが今、相続のことで少しでも不安や悩みを抱えていらっしゃるなら、どうか一人で抱え込まないでください。
下北沢司法書士事務所は、不動産会社での実務経験と宅地建物取引士としての登録もある司法書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いします。法律や計算の面から多角的に課題を分析するだけでなく、あなたの不安や辛いお気持ちにもしっかりと寄り添い、ご家族全員が納得できる最適な解決策を「一緒に考えて提案する」パートナーでありたいと願っています。
手続きの煩わしさや精神的なストレスからあなたを解放し、穏やかな未来へ進むためのお手伝いをさせていただけませんか。ぜひお気軽にご相談ください。

対応エリアも事務所のある世田谷区や東京23区のほか、神奈川・埼玉・千葉・茨城での首都圏や神戸・札幌など全国出張も行っております。
主な対応エリアはこちら↓
ぜひ電話やお問合せフォームでお気軽にご相談ください!

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。