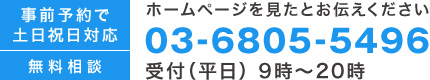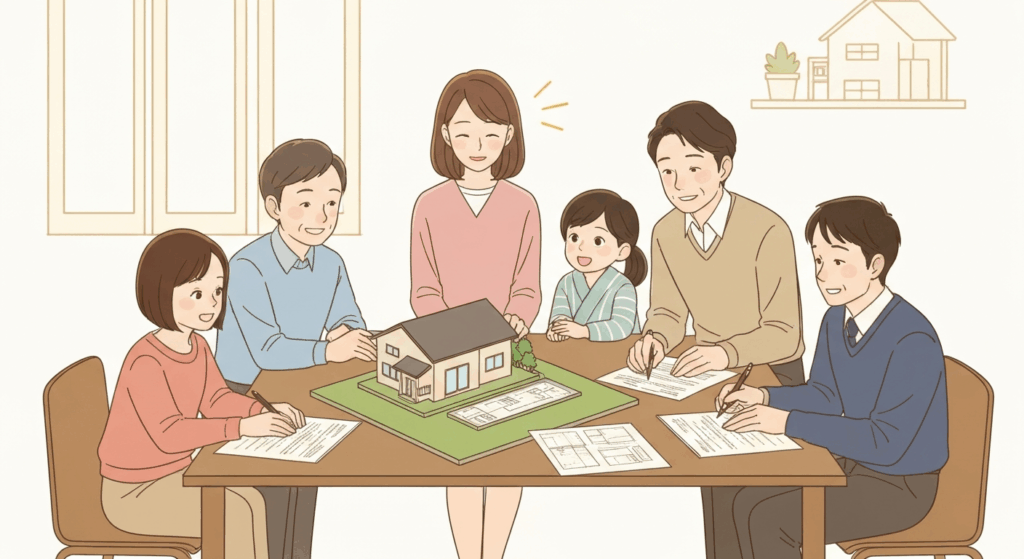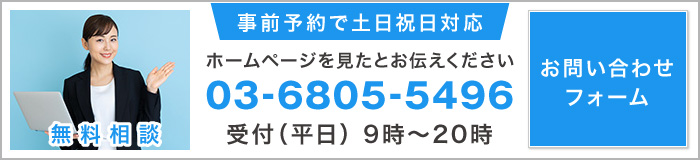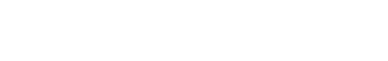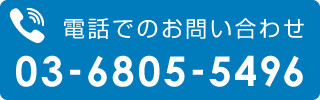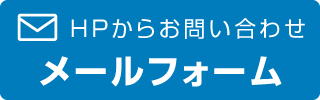相続人が複数…不動産を売却してお金で分ける「換価分割」とは?
「親が遺してくれた実家、相続人は兄弟姉妹で複数いるけれど、誰も住む予定がない…」「どうやって公平に分けたらいいのだろう…」
大切なご家族が亡くなられた悲しみに加え、このような不動産の相続問題は、多くの方にとって頭の痛い悩みではないでしょうか。特に相続人が多ければ多いほど、全員が納得する形で話を進めるのは簡単なことではありません。
そんなとき、とても有効な解決策となるのが「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法です。これは、相続した不動産を売却して現金に換え、その現金を相続人同士で分け合う方法のことです。
この記事では、司法書士であり、不動産会社での実務経験も持つ筆者が、多数の相続人がいる不動産を円満に売却するための「換価分割」について、具体的な手順や注意点を一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、複雑に見える手続きの全体像がわかり、次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。手続きの流れや注意点を丁寧にご説明しますので、まずはご一読ください。
なぜ「換価分割」が最適な選択肢になるのか?
不動産という「分けにくい財産」を前に、なぜ「売却して現金で分ける」という換価分割が、多くのケースで最良の選択肢となるのでしょうか。それには、いくつかの明確な理由があります。
- 公平で不満が出にくい
不動産をそのまま誰かが相続する(現物分割)と、「もらう人」と「もらわない人」が出てしまい、不公平感が生まれがちです。また、誰か一人が相続する代わりに他の相続人にお金を払う(代償分割)方法もありますが、不動産を相続する人に十分な資力が必要になります。その点、換価分割は売却代金を法律で定められた相続分(法定相続分)など、皆で決めた割合に応じてきれいに分けられるため、最も公平で不満が出にくい方法と言えます。 - 管理の負担や固定資産税の悩みから解放される
誰も住まない不動産は、放置すれば老朽化が進み、資産価値が下がってしまいます。定期的な管理の手間やコスト、毎年かかる固定資産税の負担は、決して小さくありません。売却することで、こうした将来にわたる身体的・金銭的な負担から解放されます。 - 相続税の納税資金を確保できる
相続税は原則として現金で納める必要があります。不動産など、すぐに現金化できない財産ばかりを相続した場合、納税資金の準備に困ってしまうケースも少なくありません。換価分割であれば、売却によって得た現金でスムーズに納税することができます。
特に、相続人同士の関係性が少し複雑であったり、それぞれが不動産に対して異なる考えを持っていたりする場合に、この換価分割は皆が納得しやすい着地点を見つけるための、とても現実的で賢い選択肢となるのです。
換価分割の難しい課題と注意点
もちろん、換価分割にも注意すべき点はあります。事前に知っておくことで、落ち着いて対策を立てることができます。
- 売却までの段取りが難しい
通常の不動産では発生しない相続手続きを完全に済ませてから売却する必要があります。そのため、何をどの順番で進めるのか段取りが重要になります。1つ1つ進めると確実ですが時間がかかり、かといって同時並行で進め過ぎて予定通りにいかない段取りがあると、購入希望者に迷惑がかかり最悪はトラブルに発展するリスクもあります。通常の不動産売却と比較して売却がより重要になります。 - 売却価格に対する合意形成
遺産分割協議の内容にもよりますが、やはり相続人全員が納得した価格で売るのが今後の関係性を踏まえても望ましいでしょう。相続は複数人が関連することが多いため、売却価格の合意形成もポイントです。 - 相続人が納得する透明性がある清算
一口に相続人で売却代金を配分するといっても、売却には経費がかかります。相続登記の費用や司法書士手数料、不動産仲介会社の仲介手数料など。これらの費用を差し引いた分をそれぞれの按分で売却するので、結局はどの人がいくら取得するのか、計算が複雑になります。みなさんが納得する透明性のある清算が大事になってきます。
これらは換価分割独特の難題デアありますが、事前に計画を立て、専門家と相談することでリスクを軽減できる場合があります。例えば、信頼できる不動産会社を選び、その不動産会社が相続担当の司法書士と密に連携し、適切な売却戦略を立てることで、スムーズな売却を目指せます。税金についても、使える特例などを事前に知っておくことで、負担を軽減できる場合があります。大切なのは、一人で抱え込まずに専門家と相談しながら進めることです。
【5ステップで解説】換価分割の進め方と全体の流れ
「何から手をつければいいのか分からない…」そんな不安を解消するために、ここからは換価分割の具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。全体像を把握することで、今やるべきことが明確になります。
ステップ1:相続人全員で「売却する」という意思を固める
手続きを進める上で、最も重要で、そして最も丁寧に進めるべきなのが、この「合意形成」のステップです。法律上、相続人全員の同意がなければ不動産を売却することはできません。
相続の話は、お金の話だけでなく、ご家族それぞれの思い出や感情が絡み合うデリケートな問題です。私自身、心理カウンセラーとして多くの方のお話を伺ってきましたが、まずは一方的に「売りたい」と主張するのではなく、他の相続人がどう考えているのか、それぞれの希望や状況に耳を傾けることから始めるのが良いでしょう。
「本当は住みたいと思っている人はいないか」「売却に不安を感じている人はいないか」など、一人ひとりの気持ちを尊重し、全員が納得できるゴールを一緒に探していく姿勢が大切です。もし、話し合いが難航しそうな場合や、感情的な対立が生まれそうなときは、私たちのような第三者の専門家が間に入ることで、冷静に話し合いを進めるお手伝いができます。
ステップ2:全員の合意内容を「遺産分割協議書」にまとめる
相続人全員の意思が固まったら、その内容を法的に有効な書面である「遺産分割協議書」にまとめます。口約束だけでは、後になって「言った」「言わない」といったトラブルに発展する可能性があります。全員が署名し、実印を押印した遺産分割協議書を作成することで、合意内容が確定し、後の手続きをスムーズに進めるための重要な証拠となります。
ステップ3:不動産の名義を相続人に変更する(相続登記)
亡くなられた方の名義のままでは、不動産を売却することはできません。遺産分割協議書に基づき、法務局で不動産の名義を相続人に変更する手続き、これが「相続登記」です。なお、2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性もあります。
このとき、登記の名義を「相続人の代表者一人」にするか、「相続人全員の共有」にするかという選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、特に税金面で注意が必要な点があるため、どちらが良いかは状況によって異なります。この点については、後ほど詳しく解説します。
ステップ4:不動産会社に依頼し、売却活動を行う
相続登記が完了したら、いよいよ不動産会社に依頼して売却活動を開始します。ここで重要なのが、不動産会社選びです。単に査定価格が高いという理由だけで選ぶのではなく、相続案件の取り扱いに慣れている、経験豊富な会社を選ぶことが手続きの円滑化に資する場合が多いです。
相続不動産の売却には、通常の売却とは異なる特有の注意点があります。担当者が相続に関する知識を持っているか、親身に相談に乗ってくれるかなどをしっかりと見極めましょう。私自身、不動産業界での勤務経験があるため、どのような会社や担当者が信頼できるか、実務的な視点からアドバイスが可能です。ご希望があれば、お客様の状況に合った不動産会社との連携もサポートいたします。
ステップ5:売却代金を受け取り、精算・分配する
無事に買い手が見つかり売買契約が成立すると、買主から売却代金が支払われます。その代金から、不動産会社への仲介手数料や登記費用、税金といった諸経費を差し引くことが一般的ですが、費用負担の詳細は遺産分割協議書や売買契約で定めます。そして、最終的に手元に残った金額を、遺産分割協議書で決めた割合に基づいて各相続人に分配します。
お金の分配は、最もトラブルになりやすい場面の一つです。だからこそ、何にいくら費用が掛かったのかを明確にした精算書を作成し、全員が納得できる透明性の高い手続きを行うことが不可欠です。私たち司法書士は、こうした最終段階での精算書の作成や、各相続人への振込が間違いなく行われるかの確認まで、責任をもって立ち会うことで、最後の不安を取り除きます。
【税務トラブル回避】換価分割のための遺産分割協議書の書き方
換価分割を円滑に進める上で、遺産分割協議書の書き方は極めて重要です。特に、手続きを簡便にするために代表者一人の名義で登記して売却する場合、書き方を間違えると、思わぬ税金の問題が発生するリスクがあります。
なぜ「換価分割のため」と明記する必要があるのか?
例えば、相続人がAさん、Bさん、Cさんの3人で、手続きの便宜上、代表してAさん一人の名義で相続登記をしたとします。その後、Aさんが不動産を売却し、その代金をBさんとCさんに渡しました。このお金の流れだけを見ると、税務署は「Aさんが相続した財産を、BさんとCさんに贈与した」と判断してしまう可能性があるのです。
もし贈与とみなされてしまうと、BさんとCさんには高額な贈与税が課せられる恐れがあります。
このような事態を避けるための、有力な方法の一つとして、遺産分割協議書に「この遺産分割は、不動産を売却して現金で分ける(換価分割)ことを目的とする」と明確に記載しておくことが推奨されます。これにより、AさんがBさん・Cさんにお金を渡す行為が「贈与」ではなく、「当初からの遺産分割」の一環であることを示す有力な資料になりますが、最終的な税務判断は税務署の見解や個別事情により異なるため、税理士と連携して対応することが重要です。また手続き面での煩雑さは増えますが、お金を受け取る割合に合わせて持分を取得する形で相続登記をすると、より安全です。
【文例付き】代表者名義で売却する場合の記載例
実際に遺産分割協議書を作成する際に、どのように記載すればよいか、具体的な文例をご紹介します。これはあくまで一般的な例ですので、実際の作成にあたっては、皆様の状況に合わせて個別に作成をします。
【記載例】
第〇条 相続人らは、被相続人〇〇(亡くなった方の氏名)の遺産である下記不動産について、換価分割することに合意し、売却手続きの便宜上、相続人〇〇(代表者の氏名)が単独で取得する。
(不動産の表示)
所在:〇〇市〇〇町…
(以下、登記簿謄本の通りに記載)第〇条 相続人〇〇(代表者の氏名)は、前条の不動産を速やかに売却し、その売却代金から譲渡費用その他一切の諸経費を控除した残金を、次の割合で各相続人に分配する。
- 〇〇(代表者の氏名):2分の1
- △△(他の相続人):2分の1
このように記載することで、代表者が不動産を一旦相続する目的が、あくまで換価分割のためであることを示す有力な資料になりますが、最終的な評価は関係機関の判断に依存します。
全員の共有名義で売却する場合の記載例
贈与税のリスクを避けるもう一つの方法として、相続人全員の共有名義で相続登記をする方法があります。この場合、売買契約などの手続きは全員で行う必要があり少し煩雑になりますが、税務上のリスクは低くなります。
【記載例】
第〇条 相続人らは、被相続人〇〇の遺産である下記不動産を、次の共有持分割合で相続することに合意した。
(不動産の表示)
(略)(共有持分)
相続人 〇〇(氏名) 持分2分の1
相続人 △△(氏名) 持分2分の1第〇条 相続人らは、前条の不動産を共同して売却し、その売却代金から譲渡費用その他一切の諸経費を控除した残金を、各自の共有持分割合に応じて取得する。
どちらの方法が良いかは、相続人の人数や関係性、手続きの手間などを総合的に考慮して判断する必要があります。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
相続不動産の売却で注意すべき税金の話
換価分割を行うにあたり、税金の知識は避けては通れません。ここでは、最低限知っておきたい2つのポイントについて、分かりやすく解説します。ただし、税金の計算は非常に専門的ですので、最終的には税理士への相談が必要となることをご理解ください。
売却益にかかる「譲渡所得税」とは?
相続した不動産を売却して利益(売却益)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。この税金は、売却した年の翌年に確定申告をして納税します。
売却益は、簡単な式で表せます。
売却益 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費:亡くなった方がその不動産を購入したときの代金や手数料などです。購入時の契約書などが見つからず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費とすることができますが、実際の取得費よりかなり低くなることが多く、税負担が重くなる傾向があります。
- 譲渡費用:売却のために直接かかった費用で、不動産会社に支払った仲介手数料などがこれにあたります。
この売却益に対して、不動産の所有期間に応じた税率をかけて税額を計算します。
税負担を軽減する「取得費加算の特例」を忘れずに
相続した不動産を売却する場合、非常に有利な特例があります。それが「取得費加算の特例」です。
これは、相続税を支払った人が、相続が始まってから3年10ヶ月以内にその相続した不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を「取得費」に加算できるという制度です。取得費が大きくなるということは、計算上の売却益が小さくなるため、結果として譲渡所得税の負担を軽減できるのです。
この特例を知っているかどうかで、手元に残る金額が大きく変わることもあります。適用には期限があるため、相続が発生したら早めに売却の計画を立てることが重要です。
当事務所のワンストップサポート事例【司法書士の関わり方】
過去に、複数のご兄弟で不動産を相続され、「売却して公平に分けたい」というご相談をいただいたケースでは、相続人様の中に遠方にお住まいの方がいらっしゃり、手続きのために何度も集まるのが難しいという状況がありました。
このようなケースでは、単に書類を作成するだけでは円満な解決は望めません。私はまず、法律的な手続きの話をする前に、相続人お一人おひとりがどのようなお考えで、何に不安を感じていらっしゃるのかをじっくりと伺うことから始めました。
その上で、換価分割が全員にとって最善の選択であることをご理解いただけるよう、作成した遺産分割協議書の案に一つひとつ解説を加え、全員が「これなら納得できる」と感じてくださるまで丁寧に説明を重ねました。
そして、売却の準備段階では、売却代金から諸経費を差し引いた後の概算金額を提示し、お金の面での不安を解消。さらに、各相続人様の振込先口座を書面で確認するなど、後のトラブルを防ぐための地道な下準備も徹底しました。
不動産の売買代金の決済当日には、私も現場に立ち会いました。買主様から売却代金が間違いなく振り込まれるのを確認し、そのお金が各相続人様の口座へ送金されるまでを最後まで見届けることで、ご依頼者様が安心して手続きを終えられるようサポートいたしました。
この事例のように、相続人間の調整から最終的なお金の分配まで、一貫して寄り添い、手続きのすべてをワンストップでサポートすることが、私たちの目指す司法書士の姿です。
私たちが提供する「心に寄り添う」換価分割サポート
多くの事務所では、遺産分割協議書の作成や相続登記までが主な業務範囲かもしれません。しかし、私たちはそこからさらに一歩踏み込み、お客様の真の安心のために、以下のような当事務所独自のサービスを提供しています。
- 相続に強い不動産会社の選定・手配
- 透明性の高い精算表の作成
- トラブル防止のための、各相続人様への振込先書面確認
- 安心のための売買決済現場への立会い
当事務所では、不動産実務や法律知識、そして心理カウンセラーとしての傾聴力に基づき、これらの支援を行っています。手続きの煩わしさや精神的なストレスからお客様を解放し、円満な相続を実現することが、私たちの何よりの喜びです。
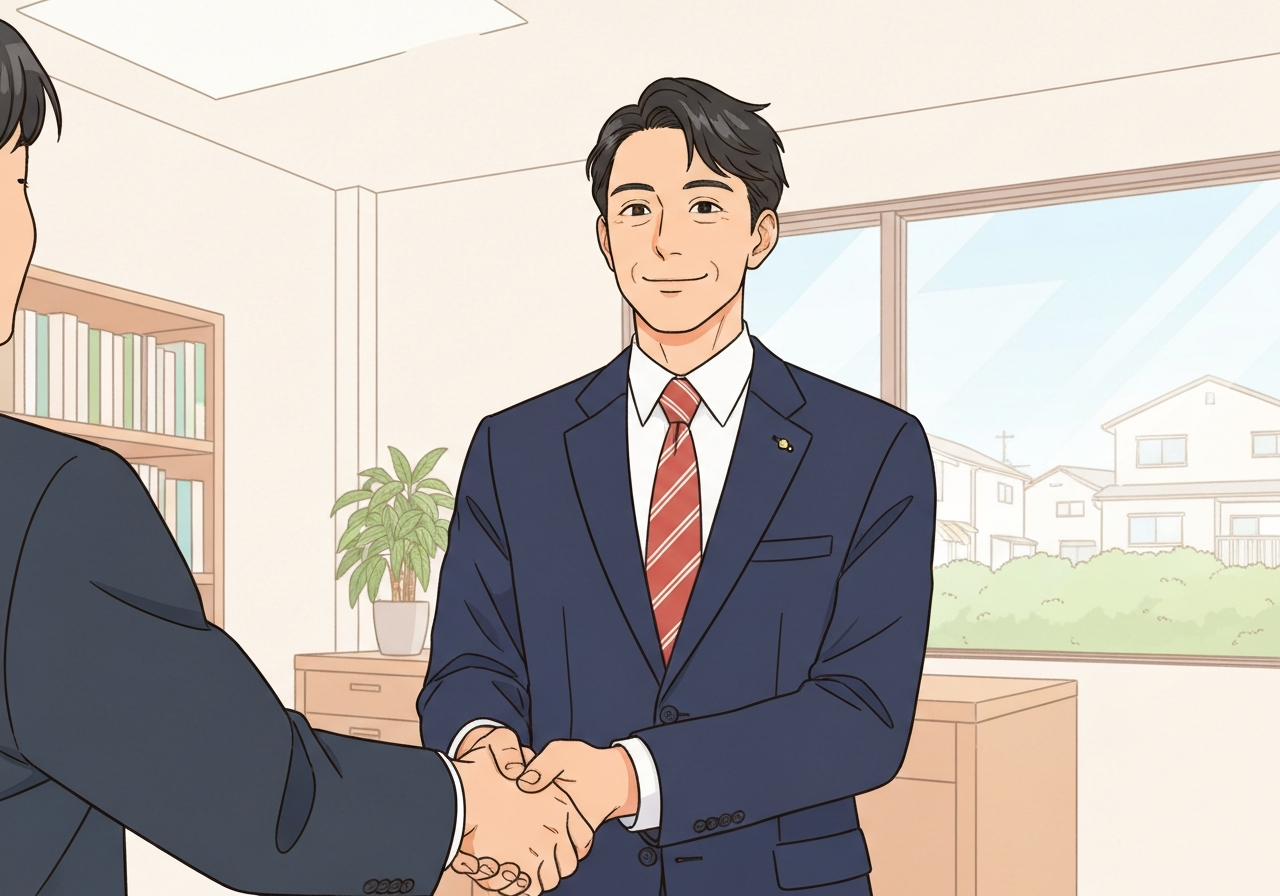
まとめ|多数の相続人がいる不動産売却は、まず専門家へご相談を
相続人が複数いる不動産の分割において、「換価分割」は非常に有効で公平な解決策です。しかし、その実現には、相続人全員の合意形成、法的に不備のない遺産分割協議書の作成、税務上のリスク回避、そして煩雑な登記・売却手続きなど、多くの専門的な知識と経験が不可欠です。
これらの問題を一人で、あるいはご親族だけで抱え込んでしまうと、思わぬトラブルに発展したり、精神的に疲弊してしまったりすることも少なくありません。
円満な解決への一番の近道は、できるだけ早い段階で私たちのような専門家に相談することです。下北沢司法書士事務所では、法律と不動産、そして心の問題にも精通した司法書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策を一緒に考えます。どうぞ、一人で悩まず、お気軽な気持ちでご相談ください。
対応エリアも、世田谷区などの東京23区だけでなく横浜や川崎、相模原、柏、松戸、さいたま市浦和などの首都圏で対応実績があります。また、出張が必要なケースのご相談も承っており、神戸・札幌・山形県鶴岡市、茨城県笠間市などで業務実績があります。
対応エリアはコチラ↓
【事務所情報】
下北沢司法書士事務所
代表司法書士 竹内 友章
東京司法書士会所属
所在地:東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。