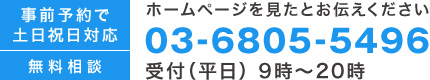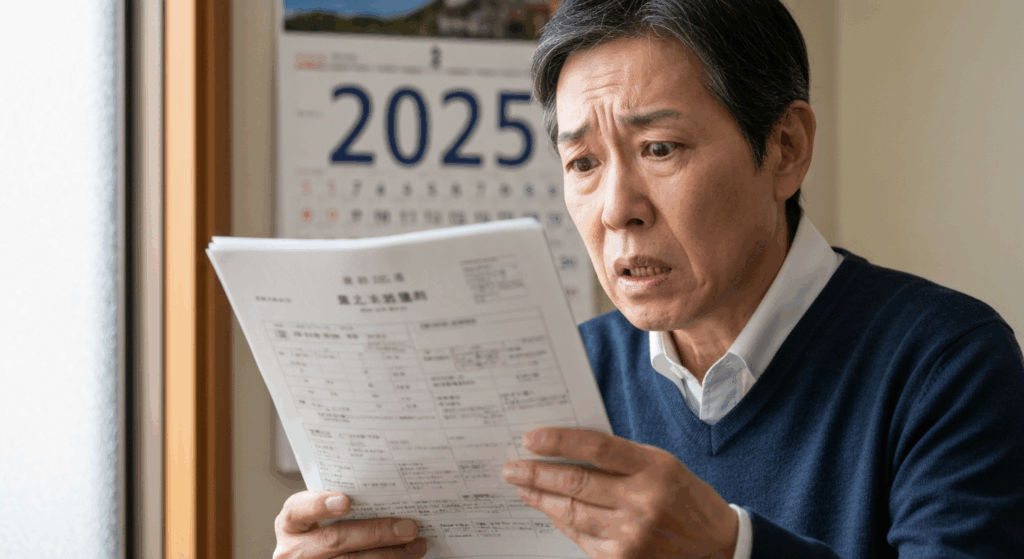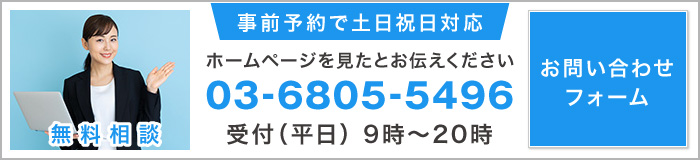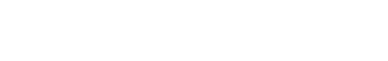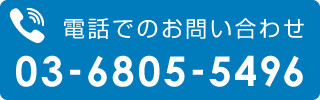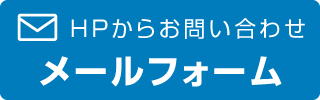相続登記のミスは「忘れた頃」に大きな問題になる
ご家族が亡くなられ、不動産の相続手続き(相続登記)を考え始めたとき、単純な名義変更と思われる方は少なくありません。しかし、相続登記には、すぐには表面化しない「隠れた落とし穴」がたくさん潜んでいます。
相続登記のミスが怖いのは、手続きを終えた直後には何も問題が起こらない点です。書類が受理され、名義が変わったことに安堵し、そのまま何年も、ときには何年も経過します。そして、忘れた頃に、その不動産を「売りたい」「担保に入れて融資を受けたい」と考えたとき、突如として「時限爆弾」が爆発するのです。
「共有持分が漏れていたため、会ったこともない親戚の同意が必要になった」
「昔の抵当権が残っていて、売却の決済日に間に合わないかもしれない」
このような事態に陥ると、売買契約が白紙になったり、急な対応で多額の費用がかかったりと、取り返しのつかない「取引事故」につながる可能性もゼロではありません。このすぐには問題が表面化しないところが、相続登記のミスの怖いところです。
この記事では、司法書士である私が、実務でよく目にする相続登記のありがちなミスを5つのケースに分けて、具体的な事例とともに解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、「あの時、ちゃんと確認しておけば…」と後悔しないための知識を身につけていきましょう。
司法書士が解説!相続登記でありがちなミス5つのケース
相続登記の手続きは、一見すると書類を集めて提出するだけの作業に見えるかもしれません。しかし、その裏には専門的な知識がなければ見落としてしまうポイントが数多く存在します。ここでは、特にご自身で手続きを進めようとする方が陥りやすい、代表的な5つのミスをご紹介します。
- 共有持分の放置・見落とし
不動産の一部(共有持分)の登記を忘れてしまい、将来の売却や活用を困難にしてしまうケースです。 - 登録免許税の計算ミス・免税措置の見落とし
税金の計算を間違えたり、使えるはずの免税制度を知らずに余分な税金を納めてしまうケースです。 - 住所変更登記の見落とし
2026年から義務化される登記ですが、相続登記と併せて行うべきことを見落としてしまうケースです。 - 抵当権抹消忘れ
完済したはずの住宅ローンなどの担保権(抵当権)が登記簿に残り続けているのを見過ごしてしまうケースです。 - 遺産分割協議書の不備
相続人全員で合意したはずの内容が、法的に不正確な書類になっており、意図しない結果を招くケースです。
一つでも「気になる」と感じた方は、ぜひこの先を読み進めてみてください。それぞれのミスがなぜ起こり、どのような問題につながるのか、そしてどうすれば防げるのかを詳しく解説していきます。
ケース1:共有持分の放置・見落とし
「亡くなった父名義の土地だと思っていたら、実は祖父の兄弟の持分が少しだけ残っていた…」これは実務で頻繁に遭遇するケースです。不動産の権利の一部である「共有持分」の相続登記を見落としたり、手続きが面倒で放置してしまったりすると、将来的に深刻な問題を引き起こします。
【放置リスク】権利者が増え続け、不動産が塩漬け状態に
共有持分を放置することの最大のリスクは、「数次相続」の発生により、関係者がネズミ算式に増えていくことです。
例えば、Aさんが亡くなり、妻Bと子C・Dが相続した不動産(持分はBが1/2、C・Dが各1/4)があったとします。このとき、妻Bの持分について相続登記をしないまま、Bさんが亡くなってしまったらどうなるでしょうか。
Bさんの持分1/2は、さらにその相続人(例えばC・D)に引き継がれます。もしCさんが亡くなれば、その持分はCさんの配偶者や子へ…。このように相続が繰り返されるたびに、権利を持つ人がどんどん増えていきます。数十年後には、会ったこともない、何十人もの親族が不動産の共有者になっているという事態も珍しくありません。
不動産を売却したり、家を建て替えたりするには、原則として共有者全員の同意と実印が必要です。関係者が数十人に膨れ上がってしまっては、全員の同意を取り付けるのは事実上不可能となり、その不動産は誰も活用できない「塩漬け」の状態になってしまうのです。

【対策】遺産分割協議で単独所有を目指すのが最善策
このような事態を避けるための最も確実な対策は、相続が発生した際に遺産分割協議を行い、特定の相続人が一人で不動産を所有する「単独所有」の状態にしておくことです。
不動産を相続する人が他の相続人に対してお金を支払う「代償分割」や、不動産を売却してその代金を分ける「換価分割」など、様々な方法があります。どの方法がご家族にとって最適かは、それぞれの状況やご希望によって異なります。
当事務所では、不動産実務の経験を踏まえた観点から分割方法の選択肢を整理し、メリット・デメリットを説明したうえでご提案します。
ケース2:登録免許税の計算ミス・免税措置の見落とし
相続登記を申請する際には、法務局に「登録免許税」という税金を納める必要があります。この計算が意外と複雑で、ミスが起こりやすいポイントの一つです。特に、本来なら利用できるはずの「免税措置」を見落として、必要以上の税金を納めてしまうケースが後を絶ちません。
登録免許税の基本計算と間違いやすいポイント
登録免許税の基本的な計算式は以下の通りです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4% (1000分の4)
「固定資産税評価額」は、毎年春ごろに市区町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に記載されている「価格」または「評価額」の欄で確認できます。
一見シンプルに見えますが、以下のような点で間違いが起こりがちです。
- 評価額の1,000円未満を切り捨て忘れる
課税標準となる評価額は、1,000円未満を切り捨てて計算する必要があります。 - 計算後の税額の100円未満を切り捨て忘れる
算出した税額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。 - 共有持分の場合の計算を間違える
例えば、評価額2,000万円の不動産の1/4の持分を相続する場合、2,000万円 × 1/4 = 500万円を課税標準として税額を計算します。
これらの細かいルールを見落とすと、税額が不足して登記申請が受理されなかったり、逆に多く払い過ぎてしまったりする可能性があります。
意外と知らない?適用できるかもしれない2つの免税措置
さらに注意したいのが、特定の条件を満たす場合に登録免許税が免除される制度です。特に見落とされがちなのが、以下の2つのケースです。
- 相続人が登記前に亡くなった場合(数次相続の免税)
例えば、祖父が亡くなり、その相続登記をしないうちに父も亡くなってしまった場合、最終的に孫が不動産を相続するケースです。この場合、本来なら「祖父→父」「父→孫」の2回分の登記が必要ですが、一定の要件を満たせば「祖父→父」の登記にかかる登録免許税が免除されます。 - 不動産の価額が100万円以下の土地の場合
相続によって取得した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、その土地の相続登記にかかる登録免許税が免除されます。これは市街化区域外の農地や山林などで適用されることが多いです。
免税措置の適用には要件がある(例:対象となるのは一定の相続ケースや土地に係る登記など)ため、当該登記が免税対象かは法務局の案内や税法上の要件を確認する必要がある。期限は令和9年(2027年)3月31日までに延長されている
ケース3:住所変更登記の見落とし
登記簿には、不動産の所有者の「氏名」と「住所」が記録されています。引越しなどで住所が変わった場合、この登記簿上の住所を現在のものに変更する手続きが「住所変更登記」です。これまでは任意の手続きでしたが、法改正により状況が大きく変わりました。
2026年4月から義務化!怠ると5万円以下の過料も
所有者不明土地問題を解消するため、法務省の施行日は2026年4月1日であり、施行前に住所等を変更した場合でも2028年3月31日までに変更登記が必要となる(詳細は法務省の「住所等変更登記の義務化」案内を参照)
この日以降は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に登記申請をしなければなりません。正当な理由なくこの義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
重要なのは、この義務は「過去の住所変更」にも適用されるという点です。つまり、法律が施行される前に住所が変わっていた場合でも、施行日から2年以内に変更登記をしなければなりません。相続を機に、ご自身の登記簿上の住所が古いままでないか、必ず確認するようにしましょう。

被相続人と相続人、どちらの住所変更が必要?
相続登記の実務で混乱しやすいのが、「誰の住所変更登記が必要なのか?」という点です。
- 亡くなった方(被相続人)の住所変更
登記簿上の住所が亡くなった方の最後の住所と異なっていても、戸籍の附票などで住所のつながりが証明できれば、住所変更登記を省略して相続登記が可能です。 - 相続する方(相続人)の住所変更
相続する不動産を元々共有で持っていた場合など、ご自身の名前がすでに登記簿に載っているケースがあります。その登記簿上の住所が古いままの場合、相続登記と一緒に住所変更登記を行うのが一般的です。これを忘れると、将来不動産を売却する際に、改めて住所変更登記が必要になり、手続きが煩雑になります。また売買登記を担当する司法書士が見落とすと、1回で登記が通らず、取引事故の原因にもなります。
相続登記は、こうした関連する手続きをまとめて整理する絶好の機会です。義務化を待つのではなく、相続登記と同時に済ませておくことをお勧めします。
ケース4・5:抵当権抹消忘れと遺産分割協議書の不備
ここまでご紹介した3つのケースの他にも、実務上よく見かける重大なミスが2つあります。それは「抵当権の抹消忘れ」と「遺産分割協議書の不備」です。
ケース4:抵当権抹消忘れ
亡くなった方が住宅ローンなどを利用して不動産を購入していた場合、完済しても自動的に登記簿から担保権(抵当権)が消えるわけではありません。金融機関から発行された書類を使って、ご自身で「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。
この手続きを忘れていると、登記簿上はまだローンが残っているように見えてしまいます。いざ不動産を売却しようとしても、抵当権が残ったままでは買主が見つからず、売却手続きを進めることができません。相続登記を行う際に登記簿を確認し、不要な抵当権が残っていれば、必ず一緒に抹消しておきましょう。

ケース5:遺産分割協議書の不備
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めた内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。この書類の記載内容に不備があると、登記申請が受理されなかったり、相続人の意図とは全く違う内容で登記されてしまったりする危険があります。
特に、ご自身で作成されたり、法務局の相談員に言われるがままに作成したりした場合にミスが起こりがちです。「不動産の表示が登記簿と一致していない」「誰が相続するのか明確に書かれていない」といった単純なミスから、「法的に無効な分割方法が記載されている」といった専門的なミスまで様々です。一度作成して全員が実印を押してしまうと、後から修正するのは非常に困難です。作成段階で専門家のチェックを受けることが、トラブルを防ぐ最も確実な方法です。
相続登記のミスを防ぐには?法務局への相談と専門家の違い
ここまで読んで、「自分一人で完璧に手続きするのは難しいかもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。では、ミスなく確実に相続登記を終えるには、どうすればよいのでしょうか。解決方法の1つに「法務局への相談」がありますが、その役割と限界を正しく理解しておく必要があります。
法務局の相談は「手続きの案内」が目的」
法務局では、登記に関する無料相談窓口を設けています。しかし、彼らの役割はあくまで、申請書の書き方や必要書類といった「形式的」な手続きを案内することにあります。立場上、個々の家庭の事情に踏み込んだアドバイスはできません。
例えば、「どのように遺産を分けるのが一番良いか」「この分け方で将来税金の問題は起きないか」「そもそも、この遺産分割協議書の内容で法的に問題はないか」といった、相続の「中身」に関する相談には乗ってくれないのです。
そのため、相談員のアドバイス通りに書類を作成しても、その内容自体がご家族にとって最適なものでないリスクがあります。法務局の相談は、あくまで手続きの流れを確認する場であり、問題解決の場ではないことを認識しておくことが重要です。質問の仕方や聞くことを間違えると、法務局の回答もあなたにとって適切なものにはなりません。
司法書士は「最適な解決」を一緒に考えるパートナー
一方で、私たち司法書士は、単なる手続きの代行者ではありません。ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、法律や税務、そして不動産実務といった多角的な視点から、将来のリスクも視野に入れた複数の選択肢をご提示し、その中から依頼者様と協議して最適と思われる選択肢を検討します。
特に当事務所では、不動産会社での勤務経験を活かし、将来の売却や活用まで見据えたご提案を得意としております。また、上級心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が、司法書士業務の範囲内で、手続きの煩わしさやご家族間のデリケートな問題から生じるご不安やストレスに関するご相談に対応し、心穏やかに手続きを終えられるようサポートいたします(ご相談内容が心理療法等の専門領域にわたる場合は、適切な専門機関をご紹介することもあります)。
どの書類が必要か、どう分ければ良いか、といった一つひとつの疑問から、不動産の名義変更(相続登記)全体の流れまで、手続き全般について専門的な立場からサポートいたします。
もし、少しでもご不安な点があれば、一人で抱え込まずに、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。
【事務所情報】
下北沢司法書士事務所
代表司法書士 竹内 友章(東京司法書士会所属)
東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201

まとめ
今回は、相続登記でありがちな5つのミスについて解説しました。
- 共有持分の見落としは、将来の不動産活用を不可能にする可能性があります。
- 登録免許税の計算ミスや免税措置の見落としは、金銭的な損失につながります。
- 住所変更登記の見落としは、法改正により過料の対象となります。
- 抵当権の抹消忘れは、売却手続きの大きな妨げになります。
- 遺産分割協議書の不備は、意図しない相続トラブルの原因となります。
これらのミスに共通するのは、問題が発覚するのが「忘れた頃」であり、その時には手遅れになっているケースが多いという点です。大切な資産を守り、次の世代に安心して引き継ぐためにも、相続登記は正確に行うことが不可欠です。
相続手続きは、ご家族にとって精神的にも時間的にも負担が大きいものです。専門家である司法書士にご依頼いただくことで、そうした負担を軽減し、可能な限りミスを防ぎ、円滑に手続きを進めることを目指します。
東京23区、千葉・埼玉・神奈川などの首都圏の方に多くご相談いただいています。遠方だと感じる方も対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。