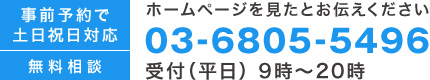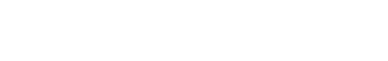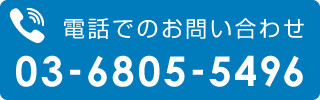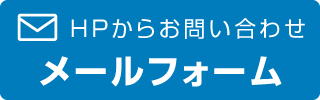Author Archive
共有不動産をどうするか?
不動産の共有状態。生じる原因として考えられるのは相続、それとご夫婦で住宅を共有で購入する場合です。今回はご夫婦でご自宅を購入された場合で考えてみましょう。お1人あたりの住宅ローンを減らすため、お2人で住宅を購入するのはよくあることです。共働きのご夫婦には効果的な方法でしょう。心配なのは夫婦仲が悪くなってしまった場合です。離婚してしまったり、あるいは離婚まではいかなくても配偶者が出て行ってしまったりしたときに問題になります。住宅ローンの負担が重いので、売ろうと思っても自分の持ち分だけではなかなか売れません(それでも売ろうと思ったら、専門の業者に安い値段で売ることになると思います)。とはいえ、出ていった夫や妻とは話ができない・・・。こんな場合が考えられます。やはり夫や妻と連絡をとり、場合によっては離婚調停も活用しながら持ち分を配偶者に売却する、持ち分を買い取る、もしくは第三者に共同で売却するのいずれかの選択をするのが基本だと思います。不動産鑑定士にご自宅の鑑定を依頼して、客観的な価格を知ることも必要かもしれません。もしきちんと居所を調べても、夫または妻と連絡がとれないときは、不在者財産管理人を裁判所に選任してもらいその管理人と共に不動産の売却するなどが考えられます。もし共有状態で困っても、解決方法はきっとあるはずです。
写真は最近買った、北沢めがね工房さんの眼鏡。甚六さんが作ったそうです。前は量販店のものを使ってましたが、素人目にも作りが全然違います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
もうすぐ司法書士試験
7月2日(日)の司法書士試験が近づいてきました。3年前に合格しましたが、「6月半ばまでに予定している勉強を終わらそう!」と考え、これくらいの時期には大体の勉強を終えていました。ただ、終わったら終わったで「問題集、もう一回解きなおそうかな」となるので結局、際限がないです。今ぐらいの試験直前は、本当に司法書士試験のことで頭が一杯でした。妻によると寝言で抵当権がどうとか言っていたようです。もし受験生の方が読んでいてくれたなら一点だけ、とても重要なポイントをお話させてください。それは、試験中最後まで戦い抜くことです。どれだけ勉強しても見たことない問題はたくさん出ます。試験を作る方もどんな勉強を受験する方がしているのか、大体わかると思いますのなかなか解けない問題を出してきます。しかし、よく見ると「聞き方が違うけれどこれは過去問だな」とか「そもそもこんなややこしい問題解かなくても他の肢で解こう」とか何かしらとっかかりがあると思いますし、全問正解させないように誰も全く分からない問題も混ぜてくるはずです。どれだけ知識があっても楽には受からせないように作ってある試験なんで、最後まで頑張ってください!サボりつつも自分なりに頑張って勉強したと思える方なら、「自分が分からないなら他の人もわからないだろう」と考えていいと思います。
偉そうに語りましたが、受かった年も試験中何が何だかわからなかったですけどね。とにかく必死に頭と手を動かすだけです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託の使い方
昨日に続いて、信託が有効な場面について考えてみたいと思います。まだ小さなお孫さんに学費などでお金を残したい場合はどうでしょうか?中学生くらいになったお孫さんにお金を渡しても遊んで使ってしまいます(言い切って申し訳ないですが、中学生のうちから学費の心配してたらちょっと立派すぎだと私は思います)。ということは、きちんと「このお金は勉強のために使うんだぞ!」と使途を限定しておく必要があります。例えば財産を息子さんに委託し財産の使用時期を高校や大学の入学時などに限定、その上で財産からあがる利益をお孫さんとしておいたらいかがでしょうか?息子さんが財産を管理したうえで、お孫さんの学費に充てられると思います。これは学費だけではなく、お孫さんに障害などがありなかなかご自身で財産を管理するのが難しい場合にも当てはまる考え方だと思います。このように信託は、財産の信託される方の想いをより忠実に再現してくれる側面もあります。法定相続、遺言と一緒に検討してみてもいいかも知れません。
お昼に回転寿司食べたんですけど、あれもこれも食べたいと思ってたくさん食べちゃいました。おなかパンパンです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
事業承継と信託
昨日に続いて、信託が有効と思われるケースを考えてみたいと思います。何の準備も無い状態で創業経営者に相続が発生してしまうと、会社の運営に支障をきたすでしょう。そこで創業経営者が、後継者を育てつつ徐々に事業を承継させたいと考えている場合。まず創業経営者が委託者(財産を預ける人)と同時に受益者(財産からあがった収益を受け取る人)になります。その上で自社株の受託者(財産を預かり運用する人)として後継者を指名します。そして預ける条件(信託の内容)として「株式の議決権は委託者の指図に従うものとする」としておけば、創業者は株主としての配当金を受け取り株主総会での決議事項は創業者に決定権を残しつつ、後継者に会社の運営を任せることが可能です。こうして後継者に徐々経営者の立場に慣れさせればスムーズに事業を承継しやすいのではないでしょうか。明日以降も、信託が有効と思われるケースについてもう少し考えてみたいと思います。
写真は昨日、お客様と打ち合わせしながら食べたお昼のハンバーグです。サラダバーでしっかり野菜も食べたので体に対する罪滅ぼしができました(^▽^)/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託はどんな時に使うのか?
相続に関連して「信託」という言葉を聞くことが多いかも知れません。信託はその自由度の高さから複雑な設計も可能となります。自由で複雑ということは専門家でないと分かりにくいので、私も含めた士業や金融機関が積極的に皆様にお知らせし、仕事につなげようとしている側面は正直あると思います。なので本当に信託を使うべきなのか、最後はご自身で納得のいく判断を是非お願いしたいと思います。なお、信託の基本的なご説明は4月11日のブログにも書いていますので宜しければご参照ください。さて、私なりに信託が有効そうなケースを考えてみたいと思います。例えば、相続財産のうち賃貸マンションがが複数あるケース。賃貸マンションなどの収益物件がいくつかある場合、恐らくその不動産の価値が一緒ということはないでしょう。立地や築年数などで大きく変わってくると思います。そうすると相続人1人に1物件づつ相続させたのでは公平になりません。また、収益物件は管理能力が問われるので、管理が上手な方に任せた方がいい場合もあり得ると思います。こういう場合には、相続人全員がすべての収益物件を相続人の1人に委託し、そこからあがった収益を相続人全員で分配する枠組みが考えられます。また、委託を受けるのは特定の相続人ではなく一般社団法人などの法人にしてもいいかもしれません。法人の理事として数人の相続人が就任すれば、不動産の運営も合議制とすることができます。また、個人に委託するより法人に委託した方が病気になったりすることがないため枠組みの継続性が保てます。社団法人ではなく株式会社を設立することも考えられますが、株主が亡くなると今度は株式が相続財産となってしまうので出資金や剰余金がない社団法人が最初の選択肢だと思います。
法務や税務、不公平感の解消と様々な観点から皆さんの納得がいく結論が出しやすいのが信託です。実現したい思いがいくつかあるなら検討してみてもいいかも知れません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺産分割協議について
遺産分割協議はどのように時にするべきなのでしょうか?法定相続だと1つの財産が一定の割合で相続人全員が権利を持つことになります。預貯金はうまく分配できるでしょうが、例えば車を数人で共有してしまうと売却の時に全員が同意する必要があります。このように相続財産がたくさんあったり法定相続だと不公平感がある場合以外でも、後々手続きをスムーズにするため遺産分割協議が有効な場合も考えられます。さて遺産分割協議の進め方ですが、まず大事なのは遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要であることです。法定相続人とは民法で「この人たちは相続人ですよ」と定められた方たちで、亡くなられた方の奥さんやお子さんなど近しい方なのですが、きちんと亡くなられた方の戸籍を確認してみることをお勧めします。読み方が分からないときはご相談ください。戸籍は、預貯金の名義を変えるにも必要になりますし、法定相続情報証明制度という制度も最近できました(詳しくは5月18日のブログに記載しています)。法定相続人が確定したら、内容を相続人の皆さんで確定し遺産分割協議書に記載します。協議書の体裁に関してはそれほど難しくありません。気を付けることはきちんと財産を特定することや、遺産分割協議書であることを明記すること、住所と氏名を署名し実印で押印することなどです。場合によっては、その協議内容に至った理由などを書いてもいいかも知れません。法的には意味をなしませんが、記録文書としては記載しておく意味があると思います。遺産分割協議書に限らず、法的文書には「この内容は必ず書かなければならない」という場合が多いですが、決められたこと以外のことを書いてはいけないということではありません。
昔から鼻づまりがひどく、この間久しぶりに耳鼻科に行きましたが「竹内さん、鼻曲がってるから手術でまっすぐにしないと治りませんよ」と衝撃的なことを言われました。もしもやるなら、ついでにイケメンに整形しようかと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
仮登記
仮登記という不動産登記上の技術があります。仮登記には登記が本来持っている「対抗力」という力がありません。自分が不動産を所有していることを仮登記しておいても、他の方に「この不動産をもっているのは自分ですよ」と主張できません。仮登記の効力としては、通常の登記を将来しておくことを「予約」しておくことです。もしも仮登記をした後に、他の方が通常の登記をしても仮登記に基づいて本登記をすれば、優先順位が上にできます。条文上は、必要な書類が整わない場合に優先順位だけ早めに確保したい場合、あるいは将来、契約の効力が生じる予約がある場合などにこの制度が使えるとされています。万が一、自分が購入する不動産などにこの仮登記がされていたら対応が必要です。そのままにしておくと将来、不動産を失うことになりかねません。基本的には抹消することになると思いますが、仮登記される権利の内容も様々なので、状況にあわせた対応が必要です。
昨日は割と過ごしやすかったですね。今日もあまり暑くならないと助かります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺言が無効になってしまうケース
相続人の皆さんのために、遺言を残しても無効になってしまう書き方があります。遺言の内容ももちろん大事ですが、形式面をきちんと整えて法的に有効な遺言になっているか、気をつけることも大事ですね。無効になってしまうケースをざっとあげてみたいと思います。なお、遺言には自筆する「自筆証書遺言」と、公証人という書類の存在を証明する職業の方に関与してもらう「公正証書遺言」があります。公正証書遺言の場合は形式面が整ってなくて無効になることはなかなか考えにくいですので自筆証書遺言について考えてみます。①自書されていない・・・自筆証書遺言は全文を手書きされてなければなりません。病気などで手が震える時には他人の添えてがあっても有効な場合がありますが、そういう場合は最初から公正証書遺言を選ぶべきでしょう。パソコンで作成された場合も自書とは言えません。全部手書きで書くので結構大変です。②日付が書いていない・・・日付は忘れがちだと思いますが、これも忘れると無効になってしまいます。ゴム印などを使用しては駄目で日付も手書きする必要があります。③氏名が書いていない・・・これも手書きで書かないと無効です。名前はそんなに意識しなくても忘れなさそうですね。ちなみに本人だと特定できればニックネームみたいな通称でもいいようです。とはいえ戸籍上の氏名ならば間違いはないので、きちんと戸籍上の氏名を書くべきだと思います。④押印されてない・・・印鑑も押してないと無効です。認印でも一応有効とされますが、実印で押印することをお勧めいたします。
大きなポイントはこの4つです。後は無くても無効になるわけではありませんが契印(割印)もした方がいいでしょう。また、書き間違いをした時も訂正の方法が決まっています。形式面で「もしかして無効になるかも知れない」と心配が残るようなら公正証書遺言にした方がご安心につながると思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
なぜ不動産登記をするのか?
住宅を購入すると発生する不動産登記。おそらく仲介業者や売り主さんから司法書士を紹介されて、そのままその人の言うとおりに何となく住民票や印鑑証明書など書類を揃えてサインをして・・・という感じで淡々と進むと思います。この淡々と進む手続きは何のためにするのか、私なりの言葉でまとめてみたいと思います。まず日常生活の中で絶対意識しませんが「自分の物である」ということと「自分のものだと他人に主張する」のは法律上別の概念です。「自分の物だと他人に主張する」ことを「対抗する」と言いますが、この対抗するためには自分名義で登記をすることが必要です※。不動産取引の際には「お金を払って自分のものになった。しかし、第三者に自分の不動産だと主張できない」空白の時間帯がどうしても生じてしまいます。お金を払ってから、登記の申請をするまでの間ですね。なので、不動産取引において良い司法書士は「不動産の購入者に信頼いただける」司法書士だと思います。もちろん、売り主さんに信頼されることも非常に大事です。しかし、売り主さんは「お金が振り込まれるまで司法書士を取引現場に待機させる」ことによって一応の安全は確保できますが、購入者はそこから司法書士がしっかり登記申請してくれるまではどうやっても権利の空白が生まれてしまいます。こうして、文章にまとめてみると不動産取引の際に「司法書士って何する人なの?」と皆さんが思われることは非常に良いことのような気がしてきました。日本で不動産取引が安全に行われるのは当たり前であるからこそ注目されないのだと思います。もしも、不動産取引に関する事件がしょっちゅう起きていれば「誰を担当司法書士にするか?」は取引上の重要なポイントになってしまう気がします。
※参考 民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
今回は鼻息も荒く条文まで載せてみました。司法書士事務所のブログらしくなったでしょうか?
下北沢司法書士事務所 竹内友章
株式会社-残余財産の分配請求権
株式会社は当然、株を発行しますが同一の会社において数種類の株式を発行することも可能です。「普通株式と比較して、どのように違う株式を発行できるか?」について会社法108条において、9種類定められています。その中の1つ「残余財産分配請求権の優先株式」。いつか会社を清算するときに、普通株式の株主より優先して残余財産の分配を受けられます。ちょっとややこしいですが、①創業して②会社が成長し出資者が登場③他の会社に、自社を売却する(吸収合併される)という展開を想定してみましょう。1人で出資して資本金100万円の会社を創業したとしても、出資者が現れる時は企業価値が10倍の1000万円になっているかもしれません。新たな出資者は創業者の10倍のお金を出して株式を買うことになります。じゃあこの会社を「1500万で買います」という方が現れたらどうでしょうか?創業者と出資者で半分づつ株式をもっていたらそれぞれ750万円づつお金を手にします。創業者は「750万円ー100万円」で600万円得します。しかし、出資者は「750万円ー1000万円」で250万円損します。これでは出資者は売却に同意しません。しかし出資者の手にする株式が「会社を清算するときはまずは、1000万円優先して配当を受ける。残りの財産を普通株式の株主と1対1で分ける」との内容だったらどうでしょうか?まずは出資者が投資額の1000万円を手にし、残った500万円を2人で分けます。創業者は500万の半分の250万円から創業時に投資した100万円をひいて150万円のプラス、出資者は250万円のプラスなので創業者も出資者も得をすることになりますね.これなら話がまとまるかも知れません。仮定に仮定を重ねてしまってますが、こんなことも起こりえます。出資者と投資契約を結ぶときは契約内容を良く擦り合わせる必要があると思います。
仕事上、よくいく法務局世田谷出張所の写真です。この建物の2階に法務局がありますが、新しくとても綺麗な建物です。
下北沢司法書士事務所 竹内友章