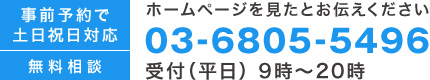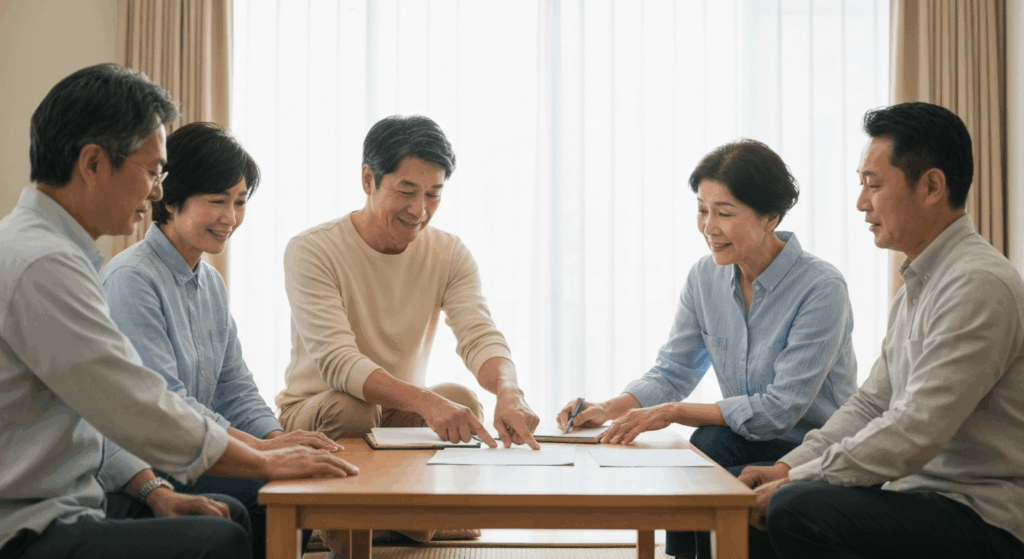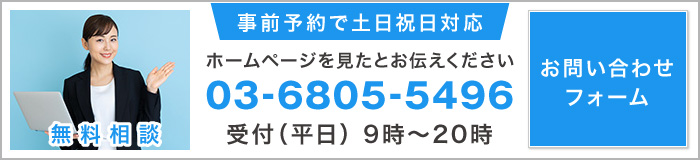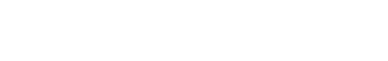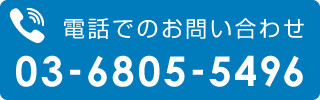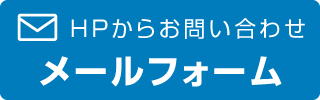なぜ遺産分割協議は「全員の合意」が絶対に必要なのか?
ご親族が亡くなられ、相続が始まると、多くの方が「遺産分割協議」という言葉を耳にします。これは、亡くなられた方(被相続人)の遺産を、どの相続人が、どのように引き継ぐのかを話し合う手続きです。そして、この協議で最も重要かつ、時に最も困難となるのが「相続人全員の合意」という点です。遺産分割協議書が法務局や金融機関といった第三者に対して効力を持つためには、原則として相続人全員の署名押印が必要となります。
「なぜ一人でも反対すると進まないのか…」と、途方に暮れてしまう方も少なくありません。法律がこのように定めているのには、一応の理由があります。それは、相続人一人ひとりの権利を尊重し、公平性を確保するためです。特定の相続人の意見だけで遺産の分け方が決まってしまえば、他の相続人が不利益を被る可能性があります。そうした事態を防ぎ、すべての相続人が納得した上で財産を承継するために、全員の合意が絶対的な条件とされているのです。
しかしながら現実の遺産分割協議をするとなると、このルールが理不尽に感じたり大きな課題に感じたりする場合もあります。今日はそのようなケースについてご紹介します。
実務の盲点:1人の「お金が欲しい」が協議を振り出しに戻すことも
最初に、当事務所が経験した遺産分割協議に全員の合意が必要なことで実務で経験したケースをお話しさせてください。この時は問題ありませんでしたが、場合によってはまとまりかけていた話し合いが振り出しに戻ってしまうと感じたケースです。
遺産分割協議は、全員の合意が原則です。そのため、たとえ相続人のうちの一人だけが「私は不動産も預金もいらないから、その代わりに少しでいいから現金が欲しい」と希望した場合でも、その内容を遺産分割協議書に明記し、全員が署名・押印しなければなりません。このケースを経験しました。1人が自宅不動産を相続することに相続人全員が口頭で了承していたものの、1人から現金の要望が出たのです。
ここで私がまずいかなと思ったのが、その協議書が他の相続人の目にも触れることです。全員の合意が必要ということは全員が同じ内容の遺産分割協議書に署名することになります。当然そこには「誰誰はいくら取得する」と書かれることになるのです。そうなると、当初「私は何もいらない」と言っていた相続人が、他の相続人が代償金を受け取ることを知った途端、「それなら私も少しはもらいたい」と考えを変えてしまうことがありえると思いました。そうなると、話し合いが振り出しに戻ってしまいます。
幸いこのケースでは問題なく対応できました。私から不動産を取得予定の方にこのコラムでもお話しする「代償分割」の方法を説明。その方が中心となって相続人間の合意が取れました。もしも代償分割が難しいケースの場合、他のやり方を考えなければなりません。例えば相続分の譲渡や放棄という手法を使ったり、相続分を割合で記載して目立たないように工夫したり、家庭裁判所に対する相続放棄を活用する等検討することになったと思います。
全員合意が難しい…よくある合意を難しくさせる財産内容
長年の実務経験から、合意形成が難しくなりやすくパターンがあると感じています。今日は当事務所が合意形成が難しくなりやすいと感じる2つのケースをご紹介します。ここにあてはまってうまく合意形成できなくとも、あなたのご家庭が特別おかしいというわけではありません。よくあることなので申告になりすぎず、できるだけ気楽に構えられると良いと思います。
ケース1:不動産など「分けにくい遺産」が中心の場合
預貯金のように金額で明確に分けられるものと違い、ご自宅や土地といった不動産は物理的に分割することが困難です。遺産の大部分が不動産である場合、話し合いは特に複雑化しがちです。
例えば、以下のような状況が考えられます。
- 長男は「親との思い出が詰まった実家だから、自分が住み続けたい」と希望する。
- しかし、他の兄弟は「自分たちは住む予定がないから、公平に現金で分けたい」と主張する。
- 誰も住む予定はないが、「先祖代々の土地だから売却には反対だ」という意見も出る。
このように、不動産は「分けにくい」という物理的な特性に加え、相続人それぞれの想いや今後のライフプランが絡み合うため、感情的な対立を生みやすいのです。不動産業界での実務経験からも、不動産価値の評価方法一つをとっても意見が分かれ、協議が停滞するケースを数多く見てきました。
ケース2:特定の相続人が親など亡くなった方の援助を多く受けていた場合
「兄は結婚しているが私は独身。結婚費用は親が援助していた。」
「妹は、親から家を買うときに多額の援助を受けていたはずだ」
被相続人の生前に、特定の相続人が財産から利益を得ていたと他の考えているケースも、協議がうまくいかないケースの典型例です。直接このことについてケンカにまではならない場合でも、心にひっかかって素直に話すことができなくなることがあります。
このような時に備えて、民法には「特別受益」という規定があります。婚姻費用や自宅不動産の建築協力など、特定の相続人が亡くなった方から利益を受けていた場合にはそのことを反映させる規定です。この規定を活用することや、「自分だけずるい」「親を独占していた」といった心理的な不公平感に配慮することがポイントです。もしかしたら、ふとしたきっかけで遺産分割協議の場が、過去の不満をぶつけ合う場になってしまうことかも知れません。

話し合いを難しくしないために知っておきたい!解決までの道筋
話し合いを難しくしないためにも、自分の家庭に照らし合わせてどのような解決方法があるのか知っておくのは重要です。ここでは主たる財産が自宅不動産の場合について検証してみたいと思います。
一番スッキリするのは売却してお金で分ける、元々そこに住んでいた方は売却で得た取得分を元手に新居を探すことです。ですが今日はそれ以外の手段で代償分割を紹介します。
解決策1:不動産を相続する人が差額を支払う「代償分割」
ケース1で挙げたように、遺産に不動産が含まれる場合に特に有効な方法が「代償分割」です。これは、特定の相続人(例えば長男)が不動産をすべて相続する代わりに、その不動産の価値と法定相続分との差額を、他の相続人(次男や長女)に対して自己の資金から現金で支払う方法です。
【メリット】
- 思い出のある不動産を売却せずに維持できる。
- 他の相続人は現金で受け取れるため、公平性を保ちやすい。
【デメリット】
- 不動産を相続する人に、代償金を支払うだけの十分な資力(預貯金など)が必要。
ただし、代償分割を進める上で「不動産の評価額をいくらにするか」という点が新たな火種になることもあります。固定資産税評価額、相続税路線価、専門家による鑑定評価(時価)など、どの基準を用いるかで金額が大きく変わるため、ここでも相続人全員の合意が必要不可欠です。
代償分割を決めた後の「相続登記」手続きと注意点
代償分割を行うことで相続人全員が合意に至った場合、その内容を法的に確定させ、不動産の名義を変更するために「相続登記」の手続きが必要です。この手続きには、司法書士としての専門知識が特に重要となる注意点がいくつかあります。

まず、合意内容を証明する「遺産分割協議書」を作成します。この協議書には、「誰がどの不動産を相続するか」ということに加え、「不動産を相続する代償として、誰が誰にいくら支払うか」という代償分割の事実を明確に記載する必要があります。この記載が曖昧だと、後々のトラブルの原因になりかねません。
そして、注意すべき点の一つに「贈与税」の問題があります。代償分割に伴う代償金は、通常は遺産分割の一環として扱われ贈与税の対象とはなりませんが、遺産分割協議書にその旨が明確に記載されていなかったり、代償金の額が不動産の価額に対して過大であったりするなど、実質的に贈与とみなされる場合には、贈与税が課税される可能性があります。
相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されました。原則として「不動産を相続で取得したことを知った日」または「遺産分割が成立した日」から3年以内に申請が必要となります。なお、2024年4月1日より前に開始した相続で未登記のものについても義務化の対象となり、3年間の猶予期間(2027年3月31日まで)が設けられています。過去コラムで複雑な案件に対するコラムも上げております。相続人が多数・不明でも大丈夫!相続登記義務化の解決事例
よろしければこちらもご覧ください。
どうしても合意できない場合は「遺産分割調停・審判」
相続人間での話し合いがどうしてもまとまらない、あるいは感情的な対立から話し合いにすらならない場合の最終的な解決手段として、家庭裁判所の手続きを利用する方法があります。なるべくなら避けたい方法だと思いますが、もしも当事者間だけの話し合いでは解決しない場合、検討するほかありません。この状況に備えて当事務所で相続に強い提携の弁護士事務所があり、状況に応じてご紹介しています。
遺産分割調停
まずは「調停」から始まります。これは、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が中立的な立場で間に入り、各相続人から個別に事情を聞きながら、解決案を提示したり、助言をしたりして、話し合いによる合意を目指す手続きです。あくまで話し合いがベースであり、第三者が介入することで当事者も冷静になり、解決に至るケースは少なくありません。
遺産分割審判
調停でも合意に至らなかった場合、「審判」手続きに移行します。審判では、裁判官が各相続人の主張や提出された資料などを基に、法律に従って遺産の分割方法を決定します。これは、当事者の合意ではなく、裁判所の判断によって結論が出されるという点で調停とは大きく異なります。
「裁判
参考:遺産分割調停 | 裁判所
まとめ:遺産分割、相続登記のご相談はぜひ司法書士へ
今日見てきたように、思いのほか相続登記や遺産分割協議には法律的に大変な部分もあります。「遺産分割協議書は全員の合意が必要」はネットを見れば出てきますが、それによってどんな課題が出るのかまでは司法書士や弁護士さんでないと気づけないこともあります。大事なのは、早い段階から専門家に相談することです。司法書士は、弁護士さんより敷居が低く相談したところで相続争いが生じているような雰囲気にもなりません。相続が発生して不動産があったらまずは司法書士に相談し、あなたのご家庭のケースでどのような段取りが適切なのか、一緒に考えていきましょう!
ご相談は初回無料相談はこちらからご利用いただけます。
対応エリアも東京23区だけはありません。東京都下や首都圏(神奈川・千葉・埼玉)でも業務実績があります他にも茨城県笠間市や石岡市、千葉県館山市・神戸・札幌・山形などで実績があり、必要に応じて全国出張します。ズームなどテレビ電話の打ち合わせも対応します。
主な対応エリアはこちら↓
ぜひ電話やお問合せフォームでお気軽にご相談ください!

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。