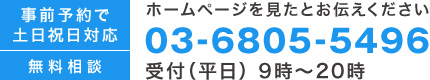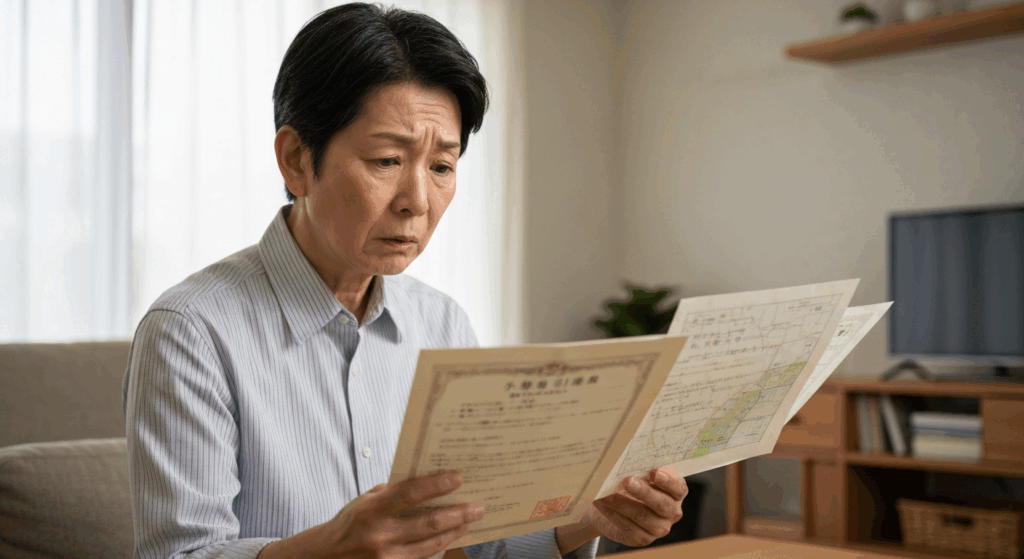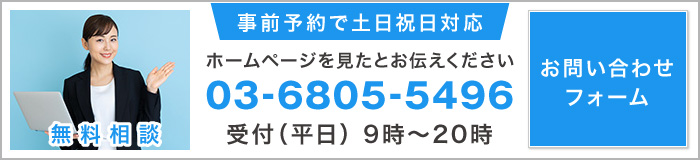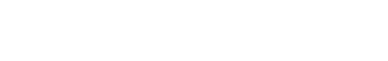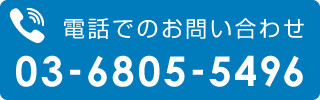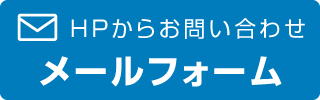相続登記の「登記漏れ」なぜ起こる?よくある失敗事例
「相続登記はしっかり済ませたはずなのに、後から登記されていない土地が見つかってしまった…」
ご両親を亡くされ、相続手続きに奔走された方から、このようなご相談をいただくことは少なくありません。特に、ご自身で手続きをされた方や、一部の手続きだけを専門家に依頼されたケースで、数年後に登記漏れが発覚する事例が見受けられます。
相続登記における「登記漏れ」とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の一部が、相続登記の手続きから漏れてしまう状態を指します。例えば、自宅の建物と土地の登記は済ませたものの、数平方メートルの私道部分の持分だけが登記されずに残ってしまう、あるいは、ご家族も誰もその存在を知らなかった遠方の山林の登記が漏れてしまうといったケースが典型です。
こうした登記漏れは、「やったつもり」という思い込みから生じることが多く、決して他人事ではありません。特に2024年4月から相続登記が義務化されたことに伴い、何十年も前に行ったはずの祖父母の相続で登記漏れが見つかり、慌ててご相談に来られる方も増えています。
この記事では、司法書士として多くの相続案件に携わってきた経験から、なぜ登記漏れが起こるのか、そしてそれを未然に防ぐための具体的な不動産調査術について、詳しく解説していきます。
専門家としての経験から:登記漏れは「思い込み」から始まる
これまでの実務で数多くの相続登記をお手伝いしてきましたが、登記漏れが発覚するケースには共通点があります。それは、ご家族の皆様が「親の財産はこれだけのはずだ」と強く思い込んでいることです。
例えば、あるご相談者様は、お父様の相続登記をご自身で完了させました。しかし数年後、自宅を売却しようとした際に、前面道路の「私道持分」の登記が漏れていたことが発覚。買主様との契約は目前でしたが、急いで相続人全員で再度、遺産分割協議を行い、私道持分の相続登記を申請する必要に迫られました。幸い、相続人間の関係が良好だったため事なきを得ましたが、もし関係が悪化していたら、売却そのものが頓挫していた可能性も否定できません。
この事例のように、登記漏れは後になって大きなトラブルの火種となり得ます。手続きの煩雑さやストレスから皆様を解放し、安心して未来へ進むためにも、最初の段階で網羅的な調査を行うことが何よりも重要なのです。
【要注意】登記漏れしやすい不動産リスト
では、具体的にどのような不動産が登記漏れの対象になりやすいのでしょうか。ここでは、特に注意が必要な不動産の典型例を3つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。

私道・共有道路の持分
登記漏れの代表格ともいえるのが、自宅に接している「私道」や「共有道路」の持分です。一戸建てを購入した際、土地と建物だけでなく、前面道路の所有権(多くは共有持分)も一緒に取得しているケースが一般的です。
しかし、この私道部分は、公衆用道路として利用されているなどの理由から固定資産税が非課税になっていることが多く、毎年送られてくる納税通知書には記載されてないこともあり得ます。そのため、納税通知書だけを頼りに相続財産をリストアップすると、私道の存在を完全に見落としてしまうのです。
不動産取引の実務に携わってきた経験から申し上げると、この私道持分の登記漏れは、将来その不動産を売却する際に極めて大きな問題となります。買主様への所有権移転が完全にできないため、最悪の場合、売買契約そのものが白紙撤回になるリスクも孕んでいます。
所在が分かりにくい山林や原野
ご自身の生活圏から遠く離れた場所にある山林や原野、畑なども登記漏れが発生しやすい不動産です。先祖代々受け継いできた土地で、ご自身はもちろん、亡くなった親御さんですらその正確な場所や範囲を把握していないケースも珍しくありません。
山林などは地番が「〇〇山 1番」のように大まかで、一つの地番でも複数の筆に分かれていることが多く、すべての土地を把握するのが困難です。また、価値が低いと思われている土地ほど関心が薄れ、相続手続きの際に意識から抜け落ちてしまいがちです。
マンションの敷地権や付属建物
「うちはマンションだから大丈夫」と思われている方も注意が必要です。特に、建築年月日が古いマンションの場合、現在の「敷地権付きマンション」とは異なり、建物(専有部分)の権利と、土地の権利(共有持分)が別々の登記になっていることがあります。この場合、建物の登記はしても、土地の共有持分の登記を失念してしまうリスクがあります。
また、駐車場やトランクルーム、物置などが、居住用の建物とは別の「付属建物」として独立して登記されているケースもあります。マンション管理会社での勤務経験上、こうした付属建物の存在は管理規約や購入時の書類を確認しないと判明しにくく、見落としやすいポイントの一つです。
登記漏れを防ぐカギは「複合調査」にあり
ここまで登記漏れしやすい不動産の例を見てきましたが、ではどうすればこうした見落としを防げるのでしょうか。その答えは、単一の書類に頼るのではなく、複数の公的な書類を組み合わせて多角的に調査する「複合調査」にあります。
ユーザーからの補足指示にもあったように、「名寄帳に載っていない私道持分」や「納税通知書に記載のない山林」は実際に存在します。「この書類さえ見れば完璧」という万能な書類は存在しないのです。だからこそ、それぞれの書類の長所と短所を理解し、パズルのピースを組み合わせるように全体像を明らかにしていく作業が不可欠となります。
ここからは、専門家が実践する複合調査の具体的なステップをご紹介します。
ステップ1:納税通知書と名寄帳で当たりをつける
調査の第一歩は、市区町村役場で取得できる書類から始めるのが効率的です。
まず、毎年4月~5月頃に送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」を確認します。ここには、その市区町村内で課税対象となっている不動産がリストアップされています(課税明細書)。これにより、少なくとも課税されている不動産の全体像を把握できます。
次に、同じく市区町村役場(都税事務所など)で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。名寄帳とは、ある特定の人がその市区町村内に所有している不動産をすべて一覧にしたものです。納税通知書との大きな違いは、私道や墓地など、固定資産税が非課税・減免されている不動産も記載される点です。
ただし、これらの書類には限界もあります。それは、調査できるのがその市区町村内の不動産に限られるという点です。もし亡くなった方が他の市区町村にも不動産を所有していた場合、その存在を突き止めることはできません。
ステップ2:権利証(登記識別情報)で契約内容を遡る
次に、故人がご自宅で保管されていた書類を確認します。特に重要なのが「登記済権利証」または「登記識別情報通知」です。
これらの書類は、不動産の所有権を取得した際の登記完了を証明するもので、不動産購入時の売買契約書などと一緒に保管されていることが多いです。書類の束を丁寧に確認すると、売買の対象となった物件の目録が見つかることがあります。その目録に、自宅の土地・建物のほかに、私道持分や付属建物などが記載されていないかを確認することで、登記漏れのヒントが得られます。
ただし、これらの書類はあくまで「購入時点」の情報です。その後に一部を売却したり、分筆・合筆したりしている可能性もあるため、必ず次のステップで最新の情報を確認する必要があります。
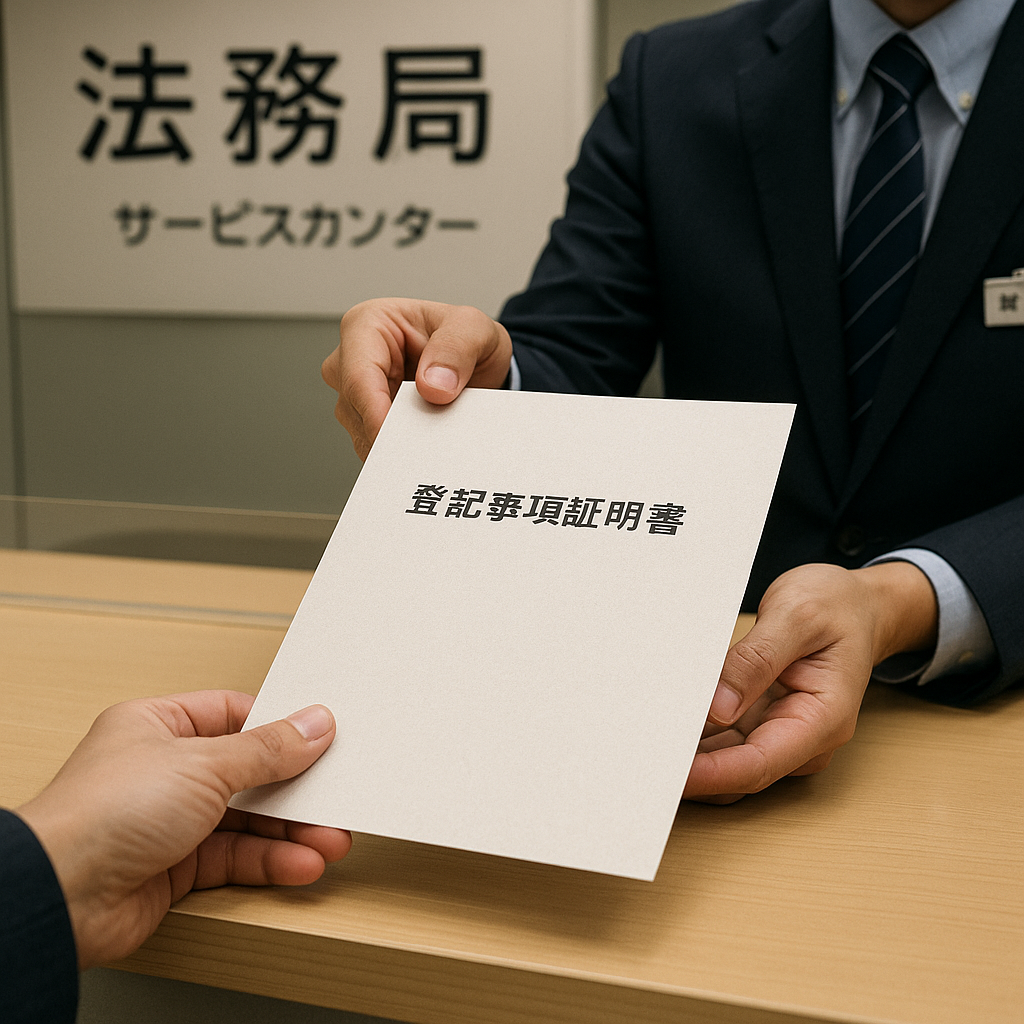
ステップ3:登記事項証明書や公図で最終確認する
最終的な確認は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。法務局では、不動産の現在の権利関係が記録された「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得できます。
ここで専門家ならではのチェックポイントとなるのが「共同担保目録」です。もし亡くなった方がその不動産を購入する際に住宅ローンなどを利用していた場合、登記事項証明書と一緒に共同担保目録を取得できます。この目録には、融資の担保として提供された不動産がすべて記載されています。
金融機関は融資の際に担保漏れがないよう厳しくチェックするため、この共同担保目録に、ご家族が把握していなかった私道持分などが記載されているケースがよくあります。これは、登記漏れを発見するための非常に有力な手がかりとなります。
さらに「公図」を取得し、対象不動産の隣接地の状況を確認することも有効です。公図を見ることで、前面道路が私道かどうか、隣接地との位置関係などを視覚的に把握でき、調査の精度が上がります。
参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
登記漏れが発覚したら?放置するリスクと対処法
もし、これらの調査によって登記漏れが発覚した場合、絶対に放置してはいけません。登記漏れをそのままにしておくと、以下のような様々なリスクが生じます。
- 売却や担保設定ができない:いざ不動産を売りたい、あるいはそれを担保にお金を借りたいと思っても、登記上の所有者が亡くなった方のままでは手続きを進めることができません。
- 次の相続で手続きがさらに複雑化する:登記漏れを放置したまま相続人が亡くなってしまうと、関係者がネズミ算式に増えていきます。そうなると、遺産分割協議をまとめるのが極めて困難になり、解決までに多大な時間と費用がかかることになります。関係者が多くなりすぎてお困りの方は、「相続人が多数・不明でも大丈夫!相続登記義務化の解決事例」の記事もご参照ください。
- 過料(罰金)の対象になる可能性:2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内(相続の開始を知った日から3年以内)に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは過去に発生した相続にも適用されるため、古い登記漏れも対象となります。
もし登記漏れが見つかったとしても、決して焦る必要はありません。改めて相続人全員で、その漏れていた不動産について再度、遺産分割協議を行い、法務局に相続登記を申請することで、適切に手続きを完了させることができます。手続きが複雑で分からない場合は、速やかに専門家へ相談しましょう。
相続登記は専門家への相談が確実です
ここまで、相続登記の漏れを防ぐための調査方法について解説してきました。しかし、ご紹介した「複合調査」をご自身で行うには、多くの時間と手間がかかります。また、古い権利証や公図を正確に読み解くには、専門的な知識と経験が必要です。
特に、以下のようなケースでは、ご自身での調査は困難を極める可能性があります。
- 相続財産である不動産の種類が多い、または複数の市区町村に点在している
- 山林や農地など、所在の特定が難しい不動産が含まれている
- 相続人が多い、または疎遠な親族がいる
- 古い書類しか残っておらず、情報の読み解きに自信がない
このような状況で無理に手続きを進めると、かえって登記漏れのリスクを高めてしまいかねません。
私たち司法書士は、不動産登記の専門家であると同時に、皆様の代理人として各種公的書類を取得し、網羅的な財産調査を行うことができます。不動産会社での実務経験も活かし、法律面だけでなく取引上のリスクも踏まえた上で、安全かつ確実に手続きを進めるお手伝いをいたします。
何より大切なのは、皆様が手続きの煩わしさや「何か見落としているかもしれない」という不安から解放されることです。当事務所は、流れ作業で工場のように大量に登記を量産するタイプの司法書士ではありません。最適な解決策を一緒に考えます。
相続登記に関するご不安やお悩みは、どうぞ一人で抱え込まずに、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。エリアも東京23区に限らず、首都圏や山梨・大阪・九州・北海道など全国の物件で取り扱い実績があります。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。