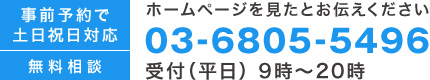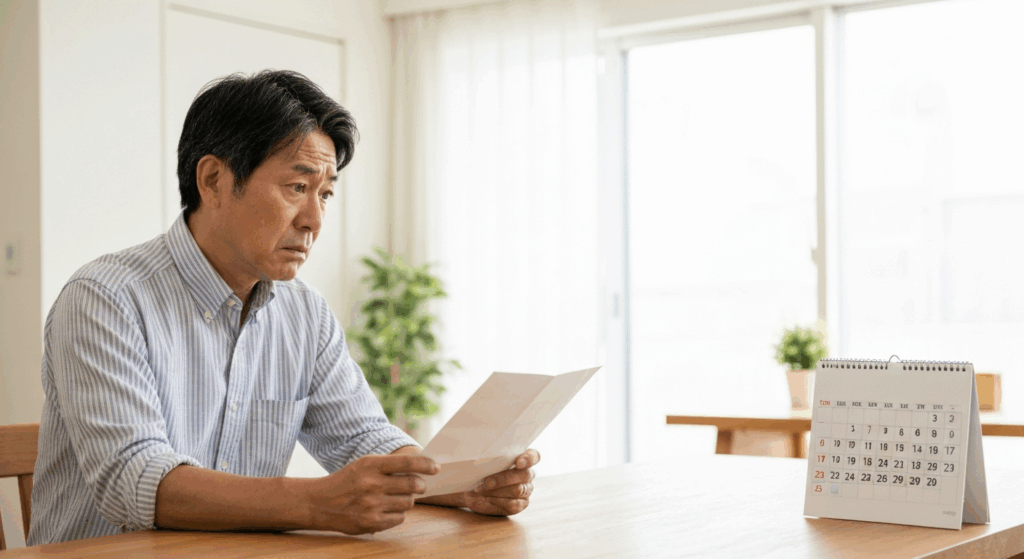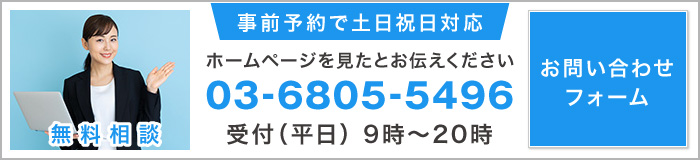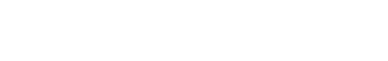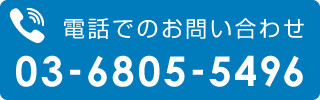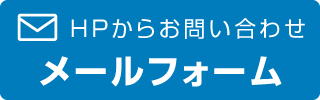他の相続人と連絡が取れない…不動産相続、最初の一歩
「兄とはもう何年も会っていないし、どこに住んでいるのかも分からない…」「叔父と連絡は取れるはずだけど、手紙を送っても返事がない…」
大切なご家族が亡くなり、不動産の相続手続きを進めなければならないのに、他の相続人と連絡が取れず、途方に暮れていらっしゃいませんか。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があると聞き、どうしていいか分からず、ただ時間だけが過ぎていくことに焦りや不安を感じていらっしゃるかもしれません。
お一人でその重荷を抱え込む必要はありません。どうかご安心ください。相続人と連絡が取れないという問題は、決して珍しいことではなく、そして、解決に向けた複数の法的手段が存在します。
この記事では、下北沢司法書士事務所の代表で、不動産実務にも精通した司法書士の竹内が、ご状況を整理するための第一歩から、具体的な解決策、そして専門家への相談まで、あなたが「次に何をすべきか」を明確にご理解いただけるよう、丁寧に解説していきます。あなたの課題解決のお役にたつので、ぜひ読み進めてみてください。
なぜ手続きが進まない?連絡が取れない相続人がいる場合の問題点
そもそも、なぜ一人の相続人と連絡が取れないだけで、不動産の相続手続きが完全に止まってしまうのでしょうか。それは、法律で定められた大原則があるからです。
亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかを話し合うことを「遺産分割協議」といいます。そして、この遺産分割協議は、必ず相続人“全員”の参加と合意がなければ、法的に有効なものとして認められません。一人でも欠けていたり、合意していなかったりする状態で行われた遺産分割協議は、後から無効となってしまいます。
この原則があるため、連絡が取れない相続人を無視して手続きを進めることはできないのです。具体的には、以下のような手続きが一切できなくなってしまいます。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 不動産の売却
- 預貯金の解約・払い戻し
- 株式などの名義変更
特に不動産は、そのまま放置しておくと管理の問題や固定資産税の負担など、新たな問題を生む原因にもなりかねません。「そのうち連絡がつくかもしれない」と問題を先送りにせず、法律に則った正しい手順で、着実に解決へ向けて歩みを進めることが大切です。
状況別|連絡が取れない相続人への具体的な対処法
「連絡が取れない」と一言でいっても、その状況は様々です。ここでは3つのケースに分け、それぞれに適した具体的な対処法を解説します。
ケース1:相続人が誰かも分からない、又は住所が分からない場合「相続人調査」
「亡くなった方に子がおらず、叔父や叔母とも長い間会っておらず全員を把握できてるわけでもない」「そもそも、どこに住んでいるのか見当もつかない」という場合は、まずその相続人の現在の住所を突き止めることから始めます。これを行うのが「相続人調査」です。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を取得し、相続人となる方を法的に確定させます。その後、対象となる相続人の戸籍をたどり、現在の住民票が登録されている住所地を記載した「戸籍の附票(ふひょう)」という書類を取得することで、現住所を調べることができます。
この戸籍の収集は、ご自身で行うことも可能ですが、非常に手間と時間がかかります。特に、本籍地が何度も変わっている場合は、全国の役所に請求手続きをしなければいけないことも多いです。また、子がいない方が亡くなった場合、あなたの従兄弟が共同相続人になる可能性も強いです。このように関係性が遠い人が共同相続人になると、その人にたどりつくため自然と集める戸籍の枚数も多くなり、読み込み方も複雑になります。司法書士ならもちろん、戸籍を読み込み正確に相続人を確定することができます。
当事務所が受任した事件・事務の遂行に必要な範囲で、職務上請求書を用いて戸籍謄本や戸籍の附票の取得を代行することが可能です。正確かつスピーディーに相続人を確定し、次のステップへ進むためにも、専門家にご依頼いただくメリットは大きいといえます。
ケース2:関係性が遠い場合、または仲が悪いケース「調整」や「遺産分割調停」
相続人同士の中が悪かったり、疎遠だったりするケースも良くあります。このようなケースに弁護士さんとは違うアプローチで対応するため、当事務所では法律だけでなく人の心理にも着目し、上級心理カウンセラーの資格も取得しました。私が経験したケースの一例をご紹介します。お子さんがいない方でなくなった奥様の相続手続きの依頼を受けました。他の相続人は奥様の縁者であり、依頼をいただいた相続人であるご主人はあまり接触がなかったようです。亡くなった他の相続人を合わせると10人強の相続人がいたものの、他の方からに対しては順調に手続きが進み、ある方を除いて遺産分割協議書や他の必要書類が揃いました。1人だけ返事がこなかった方も最初の相続に関するアンケートでは協力する旨の回答だったため遺産分割協議書をお送りしましたがその後一向に連絡がありません。おかしいなと思いつつ何回か手紙や電話で連絡してもつながりませんでした。困ったな思っていたある日、非通知で電話があり、出てみたらその方でした。「なんで何回も電話してるのに出ないんだ!」と開口一番でお叱りを受けてしまい、よく話を聞いてみると非通知で何回か電話をいただいていたようですが、私が出れなかったようです。実際に対面でお会いすることになり、30分ほどの先方から私に対する段取りなどに対する叱責、私からの遺産分割協議書は全員の合意が必要であることをはじめ民法上のルール説明の時間がありました。その後、「検討する」とおっしゃっていただき、数週間後に遺産分割協議書が届きました。このお会いした時に意識したのは話を聞くのが8割、こちらからは質問されない限り相槌と叱責に対する謝罪以外、話さないことです。会う前から何となく、具体的な手続きになにかあるというより、人に話を聞いて欲しい・・意地悪くいうと年下相手にガミガミとやりたいのではないかなと感じていました。それで納得いただけるなら私はいくらでも話を聞きます。また、あまり1つ1つ正確に事実や法的説明もしてしまうと、議論のような会話の展開になってしまうため、法的に明らかに違う部分だけやんわりと訂正をしました。はっきりいって法律の話というよりご機嫌取りであったため、人の心理の面に着目しておいて良かったなと思ったケースです。お仕事で営業職をしている方、職場の人間関係を意識しながらお仕事に取り組まれている方にはこういう「ご機嫌取り」もある意味当たり前かも知れません。しかし司法書士で、この意識をもてる人間は意外に少ないです。私たち司法書士はどうしても手続きや理屈の世界で生きています。そうするとこういう人の気持ちに対する意識が薄くなってしまい、頭コチコチになってしまうのです。しかし遺産分割協議書に押印しない理由になにも制限はありません。単に「気に入らないから署名しない」と言われれば、その後は弁護士さんによる遺産分割調停に頼る必要が出てきます。そこまでいかないようにするためには、理屈ではなく人の気持ちに気を配ることも現実問題として重要になります。
ケース3:行方不明・生死不明の場合「不在者財産管理人・失踪宣告」
長年にわたって音信不通で、生きているのか亡くなっているのかさえ分からない、という最も深刻なケースです。このような場合は、家庭裁判所に申立てを行い、法的な手続きによって状況を打開する必要があります。主な方法は2つです。
不在者財産管理人制度
従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない方(不在者)に代わって、その方の財産を管理する「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらう制度です。
この不在者財産管理人が選任されれば、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。家庭裁判所の許可を得る必要はありますが、不在者財産管理人の同意のもと、不動産を売却することも可能になります。これにより、止まっていた相続手続きを再び動かすことができます。
失踪宣告
生死が7年間明らかでない場合(普通失踪)、または戦争や海難事故などに遭遇し、その危難が去った後、1年間生死が明らかでない場合(危難失踪)に、家庭裁判所に申立てをすることで、法律上、その方を死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告が認められると、その方は死亡したと扱われるため、遺産分割協議から除外されます。もしその方に子がいれば、その子が代わって相続人(代襲相続人)となります。不在者財産管理人制度に比べて、手続きが完了するまでに時間がかかる傾向があります。
どちらの制度を選択すべきかは、状況によって異なりますので、専門家と相談しながら慎重に判断することが重要です。
不動産売却と代金分配まで一貫サポート|当事務所の約束
連絡が取れない相続人がいるという複雑な状況では、単に書類を作成するだけでは、本当の意味での解決には至りません。「問題を根本から解決し、ご依頼者様の心労と手間を極限まで減らすこと」。それが、私たち下北沢司法書士事務所の最も大切にしている姿勢です。
私たちのサポートは、法的な手続きを整えるだけで終わりません。
まず、相続人が誰なのかを調査・確定し、その方々の住所を突き止めます。そして、私たちが窓口となり、他の相続人の方々へ丁寧な書面をお送りし、相続が発生した事実と今後の手続きについてご説明します。さらに、アンケート形式でご意向を確認し、相続人全員の意思が「不動産を売却して現金で分けたい」という方向でまとまれば、遺産分割協議書の作成から署名・押印の手配まで、すべて代行します。
そして、私たちの真価が発揮されるのはここからです。
不動産会社での勤務経験を活かし、不動産の売却手続きも全面的にサポートします。売買の現場に立ち会い、所有権移転登記の申請代理・手続きは当事務所が行います。ただし、売買契約の成立や代金回収等は取引相手や契約条件に依存します。
売却代金の分配計算や振込手続きについて、事務処理を最後まで支援します。ただし、売買代金の回収や振込の可否・時期は取引の状況に依存します。
当事務所は、ご依頼者様が煩雑な手続きや慣れないやり取りで疲弊してしまうことのないよう、法律と不動産実務、そして心理カウンセラーとしての「心に寄り添う視点」を掛け合わせ、あらゆる手間と精神的なご負担を肩代わりすることをお約束します。
もし、あなたが今、どうしようもない不安の中にいるのなら、ぜひ一度私たちにご相談ください。
お問い合わせはこちら

まとめ|不安な気持ちに寄り添い、最善の解決策をご提案します
相続人の方と連絡が取れない状況での不動産相続は、精神的にも、手続き的にも、非常に大きなご負担だと思います。しかし、この記事でお伝えしたように、解決するための方法は必ず存在します。
- まずは「相続人調査」で相手の住所を確定させる
- 連絡を無視されるなら家庭裁判所の「遺産分割調停」を検討する
- 行方不明なら「不在者財産管理人」や「失踪宣告」という法的手続きがある
- どの手続きを選ぶべきか、費用や期間の見通しを立てるためにも専門家への相談が不可欠
何より大切なのは、一人で抱え込まず、信頼できる専門家をパートナーに選ぶことです。
下北沢司法書士事務所では、単に法律手続きを代行するだけではありません。不動産会社での実務経験を活かした売却サポート、そして心理カウンセラーとして皆様の不安なお気持ちに寄り添うことまで含めて、トータルで問題解決をお手伝いします。
「こんなことを相談していいのだろうか」とためらう必要は全くありません。まずはお電話やメールで、あなたの今のお気持ちを、そのままお聞かせください。そこから、解決への第一歩が始まります。ご連絡を心よりお待ちしております。
ご依頼は世田谷区をはじめとする東京23区だけでなく、調布市や町田市、小平市などの東京都下からもいただいております。相模原、川崎、横浜、柏などの首都圏でも依頼実績があります。更に出張対応では、千葉県館山市・神戸・札幌・山形などで実績があり、必要に応じて全国出張します。
主な対応エリアはこちら↓
ぜひ電話やお問合せフォームでお気軽にご相談ください!
お問い合わせ | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。