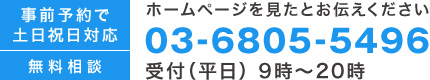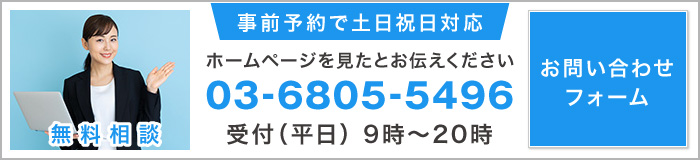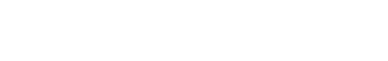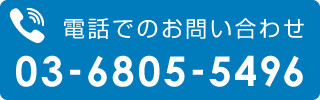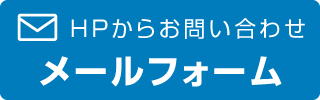「相続人が多すぎて、どうしたら…」その不安、一人で抱えないでください
「夫(妻)が亡くなって、自宅の名義を自分に変えようと思ったら、会ったこともない親戚がたくさん相続人になっている可能性があると言われた…」「相続登記が義務になったと聞いたけれど、連絡先もわからない人がいて、どう手続きを進めたらいいのか全く見当がつかない」
大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、このような複雑な問題に直面され、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。先の見えない状況に、夜も眠れないほどの不安と焦りを感じていらっしゃるかもしれません。
でも、どうかご安心ください。あなたお一人で悩む必要はありません。相続人が大勢いらっしゃったり、一部の方の行方がわからなかったりするケースは、決して珍しいことではないのです。そして、そのような複雑に見える状況でも、解決への道筋は必ずあります。
私たち下北沢司法書士事務所は、法律の手続きを進めるだけの専門家ではありません。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士として、まずあなたの不安な気持ちにじっくりと耳を傾け、心に寄り添うことを何よりも大切にしています。この記事が、あなたの心を少しでも軽くし、次の一歩を踏み出すための希望の光となれば幸いです。
【解決事例】14人の相続人を特定、全員の協力を得て自宅を守った話
「相続人が多くて手続きが進められない」というご相談は、当事務所にも数多く寄せられます。ここで、ご本人様の明確な同意を得たうえで、実際に当事務所が解決に導いたご相談者様の事例を、個人が特定されない範囲でご紹介します。このお話は、きっとあなたの状況にも重なる部分があるはずです。
ご相談者様のお悩み:ご主人が亡くなり、ご自宅の名義変更をしたい
ご相談にいらっしゃったのは、長年連れ添ったご主人を亡くされた奥様でした。お子様はいらっしゃいませんでした。多くの方が「子どもがいなければ、残された配偶者がすべて相続するのでは?」と思われがちですが、法律のルールは少し異なります。
民法の原則では、お子様がいないご夫婦の場合、亡くなった方の財産は、配配偶者が4分の3、そして亡くなった方の兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
ご主人はご高齢で、10人近いご兄弟がいらっしゃいました。さらに、すでに亡くなっているご兄弟もおり、その方々にお子さん(つまり、ご主人から見て甥や姪)がいれば、その方々も相続人となります。
どこに住んでいるのか、お元気なのかもわからない…。そんな状態から、最初の一歩を踏み出しました。
解決への道のり:丁寧な調査と「お願い」の心
私たちはまず、古い戸籍を一つひとつ丁寧にたどり、相続人が誰なのかを確定させる調査から始めました。その結果、最終的に相続人は全部で14名いらっしゃることが判明しました。
相続人を特定できても、次が最も大切な段階です。それは、お一人おひとりに事情をご説明し、奥様がご自宅を相続することに同意していただく「遺産分割協議」へのご協力をお願いすることです。
これは単なる手続きではありません。相続人の方々にとっては、突然受け取る手紙です。驚かせたり、不快な思いをさせたりすることがないよう、私たちは最大限の配慮を心がけました。故人への想い、そして残された奥様のこれからの生活を守りたいという真摯な気持ちを、丁寧な言葉で綴ったお手紙をお送りしました。
幸い、私たちの想いを汲んでくださり、14名全員が快くご協力くださいました。皆様から遺産分割協議書にご署名とご捺印をいただき、無事に奥様の名義にご自宅の登記を変更することができたのです。手続きを終えた時の、奥様の安堵された表情は今でも忘れられません。
この事例のように、たとえ相続人が何人いらっしゃっても、諦める必要はありません。大切なのは、法的な知識だけでなく、関係者一人ひとりへの敬意と、丁寧に向き合う心なのです。
なぜ相続人が増える?放置が招く「相続登記義務化」の現実
「どうしてこんなに相続人が増えてしまったのだろう?」と疑問に思われるかもしれません。その主な原因は、相続手続きがされないまま長い年月が経過し、相続が何度も繰り返される「数次相続(すうじそうぞく)」にあります。
例えば、祖父が亡くなった時に手続きをせず、次に父が亡くなり…と世代を重ねるごとに、関係者がネズミ算式に増えていってしまうのです。
こうした所有者不明の土地問題などを解決するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これからは、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に名義変更の登記をしなければならず、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。「まだ先のこと」と放置しておくことは、もはやできなくなったのです。
「3年以内」はいつから?過去の相続も対象です
この「3年以内」という期限は、いつから数え始めるのでしょうか。ルールは以下のようになっています。
- 法律の施行後(2024年4月1日以降)に発生した相続:
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内 - 法律の施行前(2024年3月31日以前)に発生した相続:
「法律の施行日(2024年4月1日)」または「相続を知った日」のいずれか遅い日から3年以内
つまり、何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産であっても、2027年3月31日までに相続登記を申請する義務がある、ということです。決して時間的な余裕があるわけではありません。
解決への3つの道筋|状況に合わせた選択肢
相続人が多数・不明な場合の相続登記には、いくつかの対応先があり、その一部をご紹介します。ご自身の状況や相続人間の関係性に合わせて、取れる中から最善の選択肢を取ることが大切です。
①【円満解決を目指す】遺産分割協議で全員の合意を得る
最も理想的で、根本的な解決につながるのが、相続人全員で話し合い、「誰がどの財産を相続するか」を決める「遺産分割協議」です。先ほどの事例のように、ご自宅を奥様お一人の名義にするためには、他の相続人全員から「自分は相続しません」という同意(実印と印鑑証明書)を得る必要があります。
この方法の最大のメリットは、不動産が共有状態になることを避け、将来のトラブルの種を完全に取り除ける点です。成功の鍵は、やはり他の相続人の方々への丁寧なアプローチに尽きます。専門家が第三者として間に入ることで、感情的なしこりを残さず、冷静な話し合いを進めやすくなります。
②【協議が困難な場合】法定相続分で登記するリスク
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合、法律で定められた相続割合(法定相続分)で、相続人全員の共有名義として登記する方法もあります。一見、公平な解決策に見えますが、これには大きなリスクが伴います。
不動産が共有名義になると、
- その不動産を売却したり、家を建て替えたりする際に、共有者全員の同意が必要になる。
- 共有者の一人が亡くなると、その人の相続人が新たな共有者となり、さらに権利関係が複雑化する。
- 固定資産税の支払いなど、管理上のトラブルが起きやすい。
不動産取引の実務を知る立場から申し上げると、安易に共有登記を選択することは、問題を先送りにするだけで、将来、ご自身やお子様の代にさらに大きな負担を残すことになりかねません。できる限り避けるべき選択肢と言えるでしょう。
③【ひとまず義務を果たす】相続人申告登記という選択
「3年以内に遺産分割協議をまとめるのは難しいけれど、ペナルティは避けたい」。そんな時に利用できるのが、2024年4月1日から始まった「相続人申告登記」という新しい制度です。
これは、相続人の一人から「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、ひとまず相続登記の義務を果たしたことになる、という簡易的な手続きです。他の相続人の協力は必要ありません。
ただし、これはあくまで一時的な措置です。この登記だけでは、不動産の所有権が確定したわけではないため、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることはできません。最終的に遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に改めて正式な相続登記を行う必要があります。
遺産分割協議に向けた時間稼ぎとして、また、ひとまず義務違反の状態を回避するための有効な手段です。
司法書士が「心に優しい」お手伝いできること
相続人が多数いらっしゃるケースでは、法律の知識はもちろんのこと、関係者の方々への細やかな配慮や、円滑なコミュニケーションが何よりも重要になります。
私たち下北沢司法書士事務所は、単に手続きを代行するだけではありません。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士として、ご依頼者様の不安な気持ちに寄り添い、他の相続人の方々へも敬意を払った丁寧な対応を徹底しています。私たちが目指すのは、手続きの負担だけでなく、「心の負担」をも軽くするサポートです。
もし、あなたが今、複雑な相続問題で心を痛めているのなら、どうぞお気軽にご相談ください。私たちと一緒に、解決への一歩を踏み出しましょう。
初回無料相談はこちら
下北沢司法書士事務所
代表 司法書士 竹内 友章(東京司法書士会所属)
〒155-0031 東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201

相続人の調査から書類作成、登記申請まで一括サポート
司法書士にご依頼いただくことで、あなたは煩雑で精神的にも負担の大きい作業から解放されます。具体的には、以下のような手続きをすべてお任せいただけます。
- 戸籍の収集と相続人調査:古い戸籍を遡り、相続人となる方を正確に特定します。
- 相続関係説明図の作成:複雑な親族関係を分かりやすく図にまとめます。
- 相続人へのご説明・協力依頼:第三者の専門家として、中立的な立場から丁寧にお手紙を作成し、事情をご説明します。
- 遺産分割協議書の作成:法的に有効で、後々のトラブルを防ぐ協議書を作成します。
- 法務局への登記申請:必要書類をすべて揃え、あなたに代わって登記を申請します。
不動産売却まで見据えた最適な解決策をご提案
当事務所の代表は、司法書士だけでなく、宅地建物取引士の資格も持ち、不動産会社での実務経験も豊富です。そのため、単に登記を完了させるだけでなく、その先の未来まで見据えたご提案が可能です。
「この家は、将来的に売却した方が良いのだろうか?」「相続した土地をどう活用すればいいのだろう?」
そんなお悩みにも、法律と不動産実務の両面から、あなたにとって最善の解決策を「一緒に考えて提案する」パートナーとしてお力になります。法律の専門家として、そしてあなたの人生に寄り添うカウンセラーとして、誠心誠意サポートさせていただきます。
対応エリアも事務所所在地である世田谷区や、東京23区だけはありません。町田市や狛江市、三鷹市などの東京都下からもご依頼をいただいております。藤沢市、川崎、横浜、松戸などの首都圏でも依頼実績があります。更に出張対応では、千葉県館山市・神戸・札幌・山形などで実績があり、必要に応じて全国出張します。ズームなどテレビ電話の打ち合わせも対応します。
主な対応エリアはこちら↓
ぜひ電話やお問合せフォームでお気軽にご相談ください!
お問い合わせ | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。