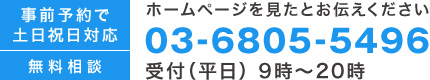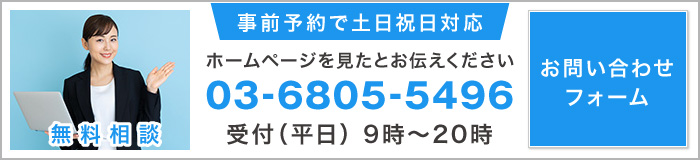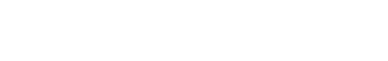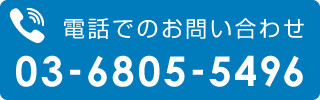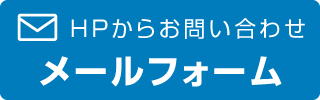こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
孫が相続人になる遺産分割協議の問題点
遺産分割のご相談で意外に多いのが、亡くなった時のお孫さんが相続人になるケース。不幸にも先に子どもが亡くなってしまい、そのまた子どもが相続人になるパターンは意外と多い。孫から見ると自分のおじさんやおばさんと一緒におじいちゃんやおばあちゃんの財産を相続することになります。こういう、本来は相続する立場の人が先に亡くなってしまうケースを「代襲相続」といいます。代襲相続が発生すると先に亡くなってしまった人の子に相続権が引き継がれるよう民法に定められています(民法887条2項、889条2項)。そして相続人になるということは遺産の分け方を決める「遺産分割協議」にも参加することになります。今日はこういうケースの注意点や課題点について解説します。
1 相続するのはあくまで「親の相続権」の範囲である
まずは勘違いしやすい知識の部分から。相続人が複数いる場合、民法で「その相続人が相続する割合」が一応決められています。これを「法定相続分」といいますが、代襲相続した人は自分の親が「生きていた本来相続する権利」を相続します。あなたがおじいちゃんの相続権をもっているとしましょう。親がおじいちゃんより先になくなり、生きていたら3分の1の法定相続分があるはずだった。その3分の1の権利をあなたは引き継ぐのですが1人で引継ぐとは限りません。あなたに兄弟がいる場合、その3分の1を兄弟と分けるのです。2人兄弟なら6分の1、3人兄弟なら9分の1があなたが引継ぐ権利の基本的な大きさである「法定相続分」になります。残念ながらおじさんやおばさんより「法定相続分」は小さくなりがちです。法定相続分を当事者の話し合いで大きさを変えたり、「不動産はAさんが引き継いて預貯金はBさんが引継ぐ」など引き継ぐ財産の種類を変えたりするのが「遺産分割協議」です。
2 遺産分割協議に参加する人数が増えやすい
代襲相続が発生する場合、亡くなった人の権利を引き継ぐのは1人とは限りません。亡くなった人のお子さんが全員遺産分割協議に参加します。つまり人数がふえがちです。人数が増えると遺産分割協議において署名・押印する人の人数が増えますから事務処理の手間が増えたり、協議をしなくてはいけない人数が増えますから一度に集まるのが大変になって連絡・意思疎通がなかなかとりにくくなったりと調整作業が複雑になりがちです。
3 遺産分割協議がまとまりにくくなる
代襲相続が発生する場合は、世代が違う人たちが遺産分割協議に参加します。世代間の違いによる感覚の違いや、普段はあまりコミュニケーションをとっていない人が協議に参加することによって、ケースによっては遺産分割協議の際の感情的な軋轢につながってしまいやすいこともあります。
4 遺産分割協議書の書き方にも一工夫が必要
どのような形で遺産を分けるか決まったら、次その内容を書類にしていきます。この書類が「遺産分割協議書」ですが、この遺産分割協議書にもできればそれぞれの立場を書いておくと後から見返したときに記録として非常にみやすい記録になります。誰が「代襲相続人」の立場で協議に参加したのか書いておくと良いです。
相続や遺産分割協議の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
今日は代襲相続の独特の課題点についてお話ししました。当事務所では相続や遺産分割協議のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。